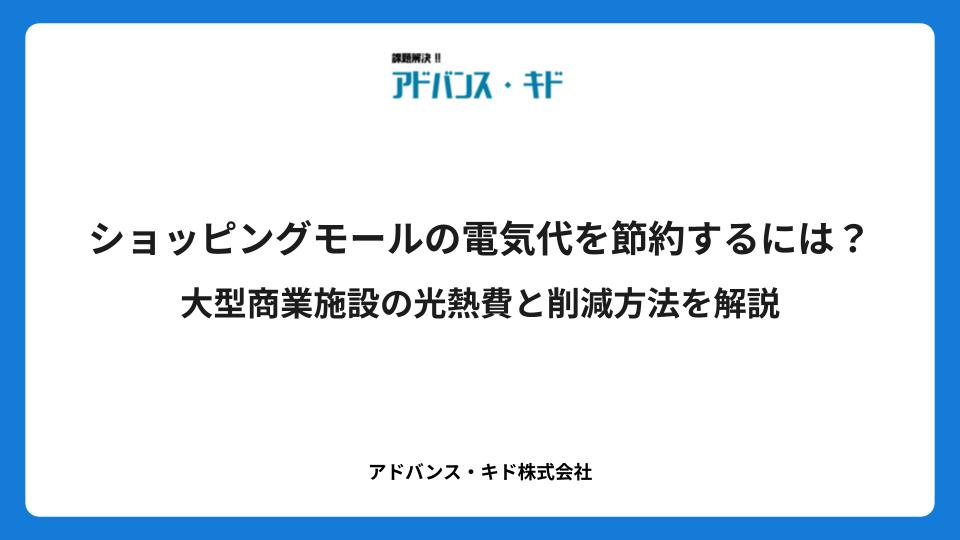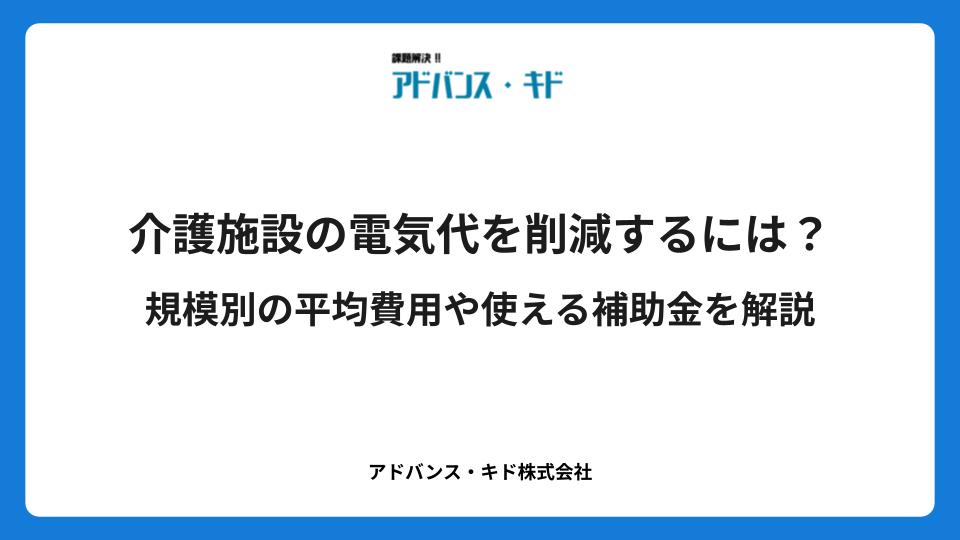記事公開日
店舗の電気代を削減するには?相場や節約方法などを解説
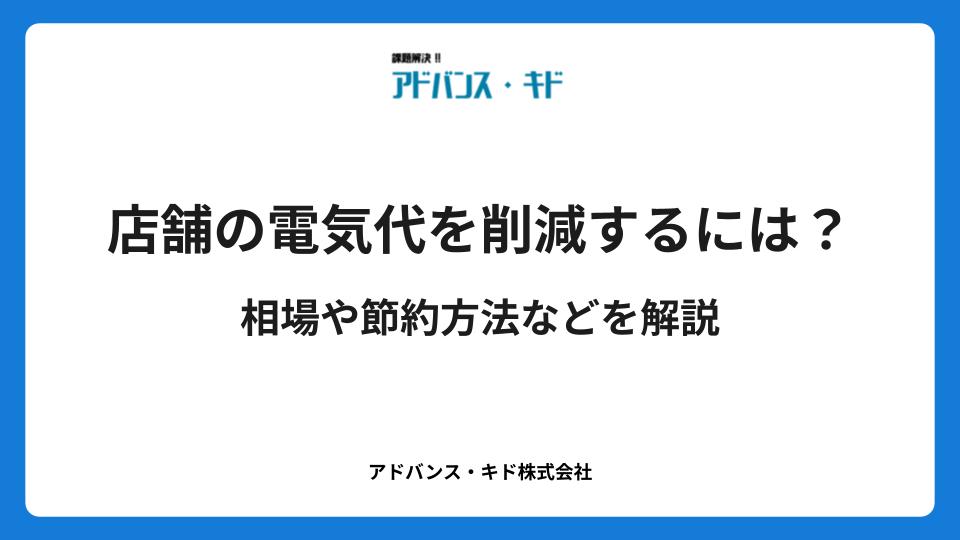
飲食店やスーパーなどの店舗において、電気代はかなり大きな支出となっています。
「電気代を減らしたい」「もっと節約できる場所はあるのか」というお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、店舗の電気代の相場を業種や規模別に分析し、高くなる主な原因を解説します。LED照明への切り替えや省エネ家電の導入、空調の効率的な使用といった具体的な節約方法から、電力会社の見直しによる大幅なコスト削減まで、明日から実践できる対策をご紹介します。
関連記事:スーパーの電気代を削減する7つの重要ポイント|今すぐ着手できるコスト削減策を徹底解説
店舗の電気代の相場はどのくらい?
店舗を運営する上で、電気代は避けられない固定費の一つです。しかし、その電気代が「適正な相場」であるかどうか把握している方は少ないのではないでしょうか。
店舗の電気代は、業種、店舗の規模、営業時間、使用する設備など、さまざまな要因によって大きく変動します。そのため、一概に「〇万円が相場」と断言することは難しいのが実情です。
しかし、ご自身の店舗の電気料金が相場と比較して高いのか低いのかを知ることは、効果的な節電対策やコスト削減の第一歩となります。まずは、一般的な電気代の構成要素として、基本料金、電力量料金(使用電力量kWhに応じた料金)、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金などがあることを理解しておきましょう。
業種別の電気代相場
店舗の電気代は、その業種が持つ特性によって大きく異なります。例えば、飲食店では冷蔵・冷凍設備や調理器具、空調設備の使用頻度が高く、電力消費量も大きくなる傾向があります。特に、24時間稼働する冷蔵・冷凍庫は、電気代に占める割合が高い要素です。
一方、アパレルショップや雑貨店などの小売店では、商品の陳列を魅力的に見せるための照明設備や、顧客の快適性を保つための空調が主な電力消費源となります。美容室では、ドライヤーやパーマ機、給湯設備、そして空調が電気代を押し上げる要因となるでしょう。
オフィスや事務所の場合、パソコンやOA機器、照明、空調が主要な電力消費となります。このように、業種ごとに電力を使用する設備や時間が異なるため、電気代の相場にも差が生じるのです。ご自身の業種における一般的な電力消費の傾向を把握することが、相場感を掴む上で重要です。
店舗規模別の電気代目安
店舗の電気代は、その規模(広さ)にも大きく左右されます。一般的に、店舗の床面積が広くなればなるほど、空調設備の稼働範囲が広がり、照明の数も増えるため、使用する電力量(kWh)が増加し、それに伴い電気代も高くなる傾向があります。
電気料金は、契約電力(kW)に応じた基本料金と、使用した電力量に応じた電力量料金の合計で計算されることが多いため、規模が大きくなれば契約電力も大きくなり、基本料金も上昇します。小規模な個人経営の店舗と、大型商業施設内のテナント店舗では、月々の電気代に大きな開きが生じるのはこのためです。
具体的な目安としては、小規模店舗であれば数万円から十数万円、中規模店舗であれば数十万円、大規模店舗では数百万円に達することもあります。店舗の規模だけでなく、天井の高さや窓の大きさといった建物の構造も、空調効率に影響を与え、結果として電気代に反映されることを覚えておきましょう。
店舗の電気代が高くなる主な原因
店舗の電気代が高騰する背景には、いくつかの主要な要因が潜んでいます。特に、日々の運営に不可欠な設備や、店舗の特性に起因する電力消費が大きく影響します。ここでは、店舗の電気代を押し上げる主な原因を具体的に見ていきましょう。
空調設備による電力消費
店舗の電気代において、空調設備は最も大きな割合を占める電力消費源の一つです。特に夏場の冷房や冬場の暖房は、外気温と設定温度の差が大きいほど多くの電力を消費します。
古い型の業務用エアコンは、最新の省エネモデルと比較して効率が悪く、必要以上に電気代がかかる傾向にあります。また、フィルターの目詰まりや室外機の汚れなども、空調効率を低下させ、電力消費を増加させる原因となります。
照明設備の電力消費
店舗の雰囲気作りや商品陳列に不可欠な照明設備も、電気代に大きく影響します。特に営業時間中、店舗全体を明るく照らし続ける必要があるため、使用する照明の種類や数、点灯時間が重要です。
また、白熱灯や従来の蛍光灯は、LED照明に比べて消費電力が非常に高く、多くの店舗でこれらの照明を使い続けていることが電気代高騰の一因となっています。装飾的な照明や看板照明も、長時間点灯することで電気代を押し上げます。
冷蔵・冷凍設備の電力消費
飲食店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど、食品を取り扱う店舗にとって、冷蔵・冷凍設備は24時間稼働が必須であり、電気代の大きな部分を占めます。これらの設備は常に庫内を一定の温度に保つため、特に外気温が高い夏場や、扉の開閉頻度が高い店舗では、より多くの電力を消費します。
また、設備の老朽化や扉のパッキンの劣化、庫内への詰め込みすぎなども冷却効率を低下させ、無駄な電力消費に繋がります。
営業時間と電気代の関係
店舗の営業時間と電気代は密接な関係にあります。営業時間が長ければ長いほど、照明や空調、その他各種設備が稼働する時間が伸び、それに伴い電気代も増加します。また、営業時間外においても、防犯用の照明や看板、待機電力として消費される電力が見過ごされがちです。
特に深夜まで営業する店舗や24時間営業の店舗では、ピークタイム以外の電力消費も考慮に入れる必要があります。
店舗の電気代を削減する具体的な方法
LED照明への切り替え
店舗の電気代削減において、照明設備のLED化は非常に効果的な手段です。従来の蛍光灯や白熱灯と比較して、LED照明は消費電力が大幅に少なく、長寿命であるため交換の手間とコストも削減できます。また、発熱量が少ないため、空調負荷の軽減にも寄与し、間接的な電気代削減効果も期待できます。
消費電力の削減: 白熱電球の約1/5~1/10、蛍光灯の約1/2~1/3程度の消費電力で同等の明るさを実現します。
長寿命: 白熱電球の約40倍、蛍光灯の約4~5倍の寿命があり、交換頻度が大幅に減ります。
発熱量の低減: 空調効率の向上に貢献し、冷房時の電気代削減につながります。
初期費用はかかりますが、ランニングコストの削減効果は大きく、長期的に見れば投資回収が可能です。自治体や国が提供する省エネ設備導入に関する補助金制度を活用できる場合もあるため、導入前に確認することをおすすめします。
省エネ家電の導入
店舗で使用する冷蔵・冷凍設備、給湯器、業務用調理器具なども、省エネ性能の高いモデルに切り替えることで電気代を削減できます。特に、稼働時間が長く電力消費量の大きい設備から優先的に見直しましょう。
高効率な冷蔵・冷凍設備: 最新の業務用冷蔵庫や冷凍庫は、断熱性能や冷却効率が向上しており、古いモデルと比較して大幅な省エネが期待できます。扉の開閉回数が多い場合は、ショーケース型ではなく、扉付きのモデルを検討することも重要です。
省エネ型給湯器: エコキュートやエコジョーズなどの高効率給湯器は、少ないエネルギーでお湯を沸かすことができ、給湯にかかる電気代(またはガス代)を削減します。
その他: 業務用の食洗機やオーブンなども、省エネ基準達成率の高い製品を選ぶことで、日々の電気代を抑えられます。
家電製品の省エネ性能は、製品に表示されている省エネラベルや統一省エネラベルで確認できます。星の数が多いほど、省エネ性能が高いことを示しています。導入時の費用だけでなく、長期的な運用コスト(ランニングコスト)を考慮して選定しましょう。
空調設備の効率的な使用方法
店舗の電気代で最も大きな割合を占めることが多い空調設備は、使い方を工夫することで大幅な節電が可能です。
適切な室温設定: 環境省が推奨する「クールビズ(室温28℃)」「ウォームビズ(室温20℃)」を目安に、快適性を損なわない範囲で設定温度を見直しましょう。夏は冷やしすぎず、冬は暖めすぎないことが重要です。
定期的なフィルター清掃: エアコンのフィルターが汚れていると、空気の循環が悪くなり、冷暖房効率が低下します。2週間に一度を目安に清掃することで、約5~10%の消費電力削減につながると言われています。
室外機の周囲環境整備: 室外機の吹き出し口や吸い込み口が物で塞がれていたり、直射日光が当たったりすると、効率が低下します。周囲を整理し、日よけを設置するなどの対策が有効です。
サーキュレーターや扇風機の併用: 空気を循環させることで、設定温度を極端に変えなくても室内全体の快適性を保ちやすくなります。
ドアや窓の開閉を減らす: 冷暖房中にドアや窓が開いていると、外気が流入し、設定温度を保つために余計な電力が必要になります。自動ドアの調整や、出入口付近にエアカーテンを設置するなども効果的です。
上記のような対策を組み合わせることで、空調にかかる電気代を効果的に削減できます。
営業時間外の節電対策
店舗が閉まっている営業時間外も、無意識のうちに電力を消費していることがあります。営業時間外の徹底した節電は、電気代削減に直結します。
照明の完全消灯: 防犯上の理由で一部の照明を残す場合を除き、全ての照明を消灯しましょう。タイマー設定や人感センサー付き照明の導入も有効です。
電化製品の主電源オフ・コンセント抜き: パソコン、モニター、充電器、一部の調理器具など、使用しない電化製品は主電源を切り、可能であればコンセントから抜くことで待機電力を削減できます。OAタップのスイッチを活用するのも手軽な方法です。
冷蔵・冷凍設備の管理: 営業時間外でも稼働し続ける冷蔵・冷凍設備は、庫内の整理整頓を心がけ、冷気の漏れを防ぐために扉のパッキン劣化がないか確認しましょう。また、営業時間終了後に庫内温度を一時的に調整する(上げすぎない程度に)ことも検討できますが、食品の品質管理には十分注意が必要です。
給湯器の設定温度見直し: 営業時間外は給湯器の設定温度を下げたり、使用しない場合は電源を切ったりすることで、保温にかかる電力を削減できます。
これらの対策は、従業員への周知と徹底が重要です。チェックリストを作成し、閉店時の確認を習慣化することで、無駄な電力消費を防ぎましょう。
電力会社の見直しで店舗の電気代を削減
店舗の電気代削減を考える上で、日々の節電努力と並んで大きな効果が期待できるのが電力会社の見直しです。2016年4月1日から電力小売自由化が始まり、一般家庭だけでなく店舗や企業も、従来の地域電力会社以外のさまざまな電力会社(新電力)から自由に電気を購入できるようになりました。この変化を最大限に活用することで、電気代の大幅な削減に繋がる可能性があります。
電力自由化のメリット
電力自由化の最大のメリットは、多様な料金プランやサービスの中から、店舗の状況に最適なものを選べるようになった点です。以前は地域ごとに決められた電力会社と契約するしか選択肢がありませんでしたが、現在は数百社もの小売電気事業者が存在し、それぞれが独自の強みを持ったプランを提供しています。
例えば、時間帯によって電気料金が変わるプラン、再生可能エネルギーの比率が高いプランなど、店舗の業種や営業時間、電力使用パターンに合わせて選ぶことで、電気代を効率的に抑えることが可能です。競争原理が働くことで、各社がより魅力的な料金やサービスを提示するようになり、消費者である店舗側にとっては有利な状況が生まれています。
店舗向け電力プランの選び方
店舗向けの電力プランを選ぶ際には、以下のポイントを比較検討することが重要です。
料金体系: 基本料金、電力量料金(従量料金)、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金など、各項目の単価を比較します。特に電力量料金は、店舗の電力使用量に直結するため、最も重要な比較ポイントです。
契約電力・契約種別: 店舗の契約電力(kW)や契約種別(低圧電力、高圧電力など)によって、選べるプランや料金体系が異なります。自店舗の契約状況を確認し、それに合ったプランを探しましょう。
契約期間と解約金: プランによっては最低契約期間が設けられていたり、期間内解約に違約金が発生する場合があります。将来的な移転や事業規模の変更なども考慮し、柔軟性のあるプランを選ぶか、解約条件を事前に確認しておくことが大切です。
電源構成: 環境への配慮を重視する店舗であれば、再生可能エネルギー由来の電力を多く供給しているプランを選ぶことも可能です。企業のCSR活動の一環としてアピールできるメリットもあります。
サポート体制: 料金に関する相談やトラブル発生時の対応など、サポート体制が充実しているかどうかも確認しておくと安心です。
複数の電力会社から見積もりを取り、自店舗の過去の電気使用量に基づいてシミュレーションを行うことで、最もコストメリットのあるプランを見つけることができます。
電力切替えなら『アドバンス・キド』の新電力
アドバンス・キドは、新電力への切り替えで年間最大30%ものコスト削減と安心の電力供給を両立させます。そのため、電気代の高騰にお悩みの法人の方にぴったりなサービスとなっております。
①最適なプランをご提案する専門性
お客様の過去1年間の電気使用状況を詳細に分析し、最適な新電力会社・電力プランを厳選します。低圧・高圧問わず対応可能で、シミュレーションにより削減額を明確にした上でご提案。多様な業種で月間23%〜36%の削減実績がある、オーダーメイドの提案力が強みです。
②市場連動型の不安を解消し、安定性を重視
電気料金の変動リスクを抑えるため、安定的な料金設定のプランを扱う新電力会社を厳選。ご要望に応じて固定料金型プランもご紹介可能です。市場データに基づいた詳細なシミュレーションで、変動リスクを分かりやすくご説明し、お客様の納得感を重視した安心できるプラン選択をサポートします。
③経営基盤が安定した「信頼できる新電力会社」のみを厳選
お客様のビジネス基盤を守るため、経営基盤が安定し、長期的な継続供給が可能な信頼性の高い新電力会社のみを厳選しています。大手商社や大手銀行が株主についているなど、財務状況が安定した企業との提携により、お客様は「倒産リスク」の心配なく安心してご利用いただけます。
電気代削減、そして削減したコストの利活用にご興味があれば、まずはお気軽に無料シミュレーションをご依頼ください。貴社の電気代がどれだけ削減できるかをご確認いただけます。
アドバンス・キドの新電力はこちら
https://www.adkd.co.jp/shindenryoku/
新電力に関するご相談・お問い合わせはこちら
https://www.adkd.co.jp/contact/
まとめ:店舗の電気代を安くするために
店舗の電気代は、業種や規模、使用する設備によって大きく変動します。電気代が高くなる主な原因を特定し、効果的な対策を講じることが重要です。
LED照明への切り替え、省エネ家電の導入、空調設備の効率的な使用など、日々の運用改善は具体的な節約に繋がります。
さらに、電力自由化を活用し、自店舗の電力使用状況に最適な電力プランへ見直すことで、より大きなコスト削減が期待できます。これらの多角的なアプローチを組み合わせることで、無理なく電気代を削減し、店舗経営の健全化に貢献できるでしょう。