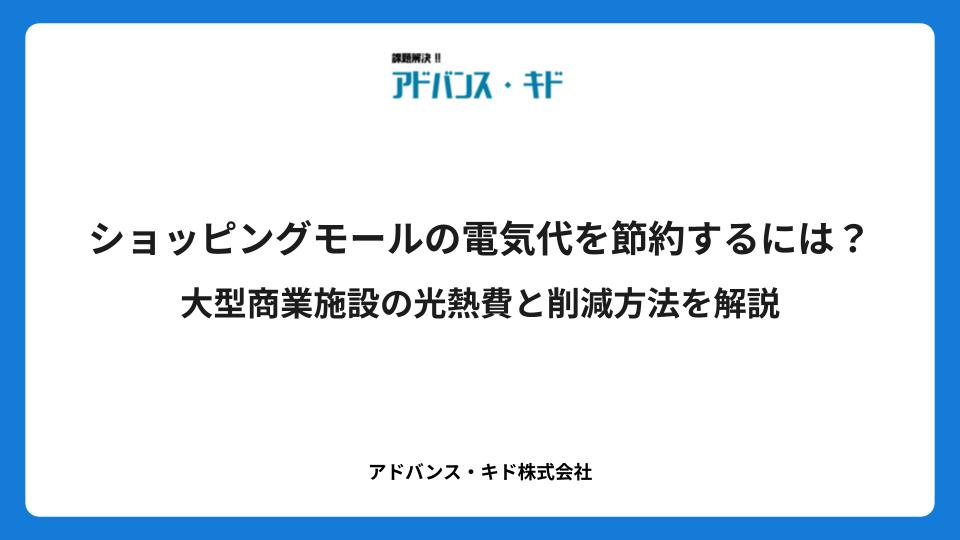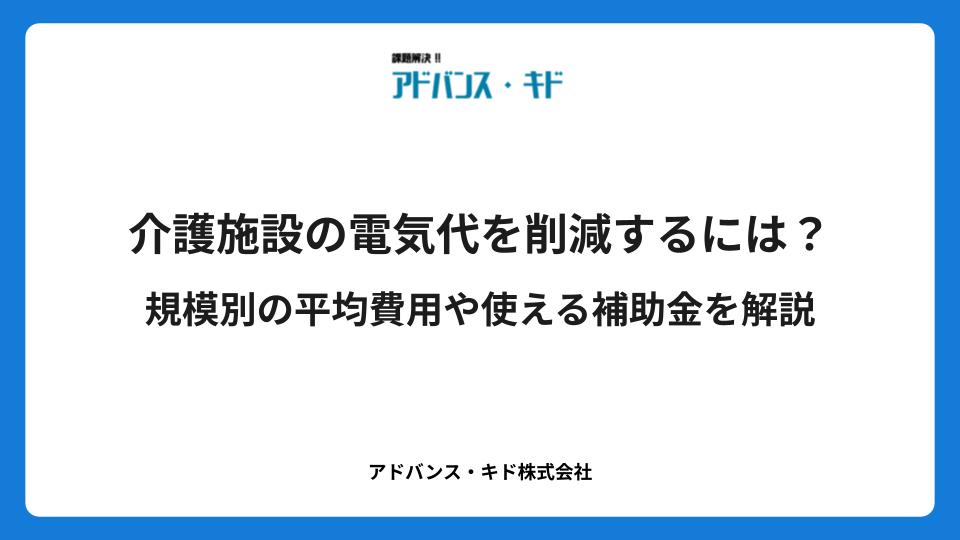記事公開日
工場の電気代を削減する方法は?相場や計算方法などを解説
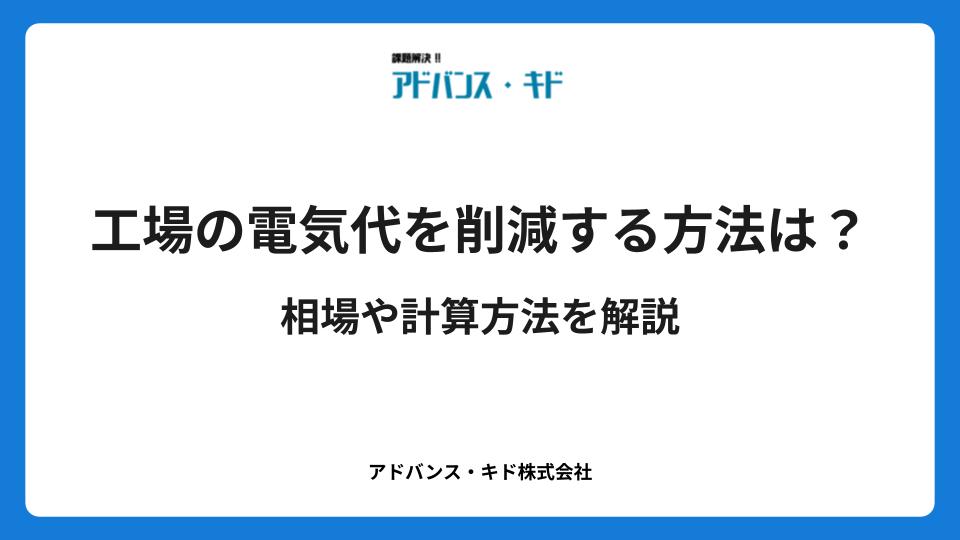
長時間稼働させる必要がある工場は、電気代に大きなコストを割いています。電気代が高騰する中、工場の資金繰りが苦しくなっているという担当者さまも多いのではないでしょうか。
本記事では、工場における電気代の相場から計算方法、高くなる主な要因まで解説します。さらに、設備機器の効率化や運用改善の方法、具体的な削減方法などをご紹介します。
工場の電気代の相場とは
工場における電気代は、事業運営において重要な固定費の一つです。その相場は、業種、工場規模、稼働状況、設備の種類など多岐にわたる要因によって大きく変動します。ここでは、製造業全体の電気代に関する一般的な傾向と、工場規模別の電気代の考え方について解説します。
製造業における電気代の平均値
工場における電気代は、生産活動に直結するため、他の業種と比較して高額になる傾向があります。多くの製造業では、生産設備の稼働、工場内の空調、照明など、事業活動のあらゆる面で電力を消費します。電気代は、原材料費や人件費と並び、製造原価の大きな割合を占める主要なコスト要因となることが少なくありません。
特定の統計データで「製造業全体の電気代の平均値」が直接的に示されることは稀ですが、一般的に、年間売上高に占める電気代(光熱費全体として)の割合は数パーセントに及ぶことが多く、特に電力消費量の多い業種や24時間稼働する工場では、その割合がさらに高くなる傾向があります。
工場規模別の電気代比較
工場の電気代は、その規模によって大きく異なります。ここでは、中小規模の工場と大規模な工場に分けて、電気代の傾向を比較します。
中小規模の工場の場合
従業員数や生産規模が比較的小さい中小規模の工場では、契約電力もそれに伴い小さくなる傾向があります。
月々の電気代の総額は、数十万円から百万円程度が一般的な目安となることが多いですが、これはあくまで目安であり、使用する設備や稼働時間によって大きく変動します。
中小規模の工場では、電力消費量の変動が経営に与える影響が大きいため、日々の節電意識や効率的な設備運用が特に重要となります。
大規模な工場の場合
従業員数百人を超えるような大規模な工場では、多数の生産ライン、大型設備、広範囲な空調・照明システムが稼働するため、月額の電気代は数百万円から数千万円に達することも珍しくありません。契約電力も数千kWから数万kWと非常に大きくなります。
大規模工場では、電気代が総経費に占める割合も大きくなるため、電力会社との契約内容の見直しや、大規模な省エネ設備投資が電気代削減の鍵となります。
また、デマンド監視システムなどを導入し、ピーク電力の抑制に努めることで、基本料金の削減にも繋がります。
工場における電気代の計算方法
基本料金と従量料金の仕組み
工場で契約する電気料金は、主に「基本料金」と「電力量料金(従量料金)」の二部料金制で構成されています。基本料金は、工場が契約している電力の最大使用量(契約電力)に応じて固定で発生する費用です。
一方、電力量料金は、実際に工場で使用した電気の量(電力量)に応じて変動する費用となります。この二つの料金に加えて、再生可能エネルギー発電促進賦課金などが加算され、最終的な電気代が決定されます。
基本料金の求め方
工場の基本料金は、契約電力と電力会社の料金単価によって決まります。特に高圧・特別高圧で受電している工場の場合、過去1年間の最大デマンド値(30分間の平均使用電力の最大値)に基づいて契約電力が決定されるのが一般的です。
契約電力と料金単価
契約電力は、契約している電力会社やプランによって算出方法が異なりますが、多くの場合、過去1年間で最も高いデマンド値(kW)が適用されます。
基本料金は「契約電力(kW) × 基本料金単価(円/kW) × 契約月数」で計算されます。この契約電力は、工場の稼働状況や設備によって変動するため、適切な管理が重要です。
デマンド監視装置の活用
デマンド監視装置は、工場全体の電力使用量をリアルタイムで計測し、最大デマンド値を監視するための機器です。
この装置を活用することで、現在の電力使用状況を把握し、契約電力を超えそうな場合にアラートを発したり、不要な設備の稼働を一時的に停止したりするなどの対策を講じることが可能になります。これにより、基本料金の無駄な上昇を抑えることができます。
電力量料金の求め方
電力量料金は、工場が実際に使用した電気の量に応じて計算される費用です。使用電力量に電力会社の料金単価を乗じることで算出されますが、燃料費調整額が加減される点も考慮する必要があります。
電力量料金の計算式
電力量料金の基本的な計算式は「使用電力量(kWh) × 電力量料金単価(円/kWh)」です。電力会社によっては、時間帯別料金や季節別料金を設定している場合があり、これによって単価が変動することがあります。例えば、昼間の稼働が多い工場では、昼間の単価が割高になるプランに注意が必要です。
燃料費調整額の考慮
燃料費調整額とは、原油やLNG(液化天然ガス)、石炭といった火力発電の燃料価格の変動を電気料金に反映させるための調整額です。燃料価格が上昇すれば加算され、下落すれば減算されます。
この調整額は毎月見直され、電気料金明細に記載されます。燃料費調整額の変動は、工場の電気代全体に大きな影響を与える可能性があるため、常に確認しておくことが重要です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の求め方
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及を促進するために、電気を使用する全ての消費者が負担する費用です。
この賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーで発電された電気を買い取る際の費用を賄うために使われます。計算式は「使用電力量(kWh) × 再エネ賦課金単価(円/kWh)」で、単価は国によって毎年見直されます。工場の電気代においては、使用電力量が大きいため、再エネ賦課金も相応の金額となります。
工場で電気代が高くなる主な要因
工場の電気代が高騰する背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。特に、生産活動に不可欠な設備やシステムが、知らず知らずのうちに多くの電力を消費しているケースが少なくありません。ここでは、工場で電気代が高くなる主な要因を具体的に解説します。
生産設備による電力消費
工場における電気代の大部分は、生産ラインを動かす各種設備機器によって消費されます。特に、モーター、コンプレッサー、ポンプ、加熱炉、工作機械といった大型の産業機械は、その稼働時間や出力に応じて膨大な電力を必要とします。
これらの設備が古い型である場合、最新の省エネモデルと比較してエネルギー効率が著しく低いことがあります。また、設備の老朽化は、本来の性能を発揮できなくなるだけでなく、無駄な電力消費を招く原因にもなります。
空調システムの負荷
工場内の温度や湿度を適切に管理するための空調システムも、電気代に大きな影響を与えます。広大な工場空間や、精密機械の稼働、製品の品質保持のために厳密な温湿度管理が必要な場合、チラーや冷凍機、大型エアコン、換気扇などが長時間稼働することになります。
空調設備の老朽化やフィルターの目詰まりは、冷却・加熱効率を低下させ、設定温度に到達させるためにより多くの電力を消費します。また、建物の断熱性能が低い、開口部からの外気侵入が多いといった構造的な問題も、空調負荷を増大させる要因です。夏場の高温時や冬場の低温時には、外気との温度差が大きくなるため、特に空調設備の電力消費量が増加しやすくなります。
さらに、適切な設定温度管理がなされていない場合も無駄な電力消費に繋がります。例えば、必要以上に低い温度や高い温度に設定したり、人のいないエリアの空調を停止し忘れたりする運用上の問題も、電気代を押し上げる原因となります。
照明設備の使用量
工場内を適切に照らすための照明設備も、電気代に少なからぬ影響を与えます。特に、広範囲を明るくする必要がある工場では、多数の照明器具が長時間点灯しています。
古いタイプの照明器具、例えば水銀灯や従来の蛍光灯などは、最新のLED照明と比較して消費電力が非常に大きいのが特徴です。これらの照明を多数使用している場合、それだけでかなりの電力を消費します。また、照明器具の点灯・消灯が適切に行われていないことも要因です。日中の明るい時間帯に不必要に点灯していたり、作業エリア外の照明が消し忘れられていたりするケースも散見されます。
さらに、人感センサーや照度センサーなどの自動制御システムが導入されていない、あるいは適切に機能していない場合、必要な明るさを確保しつつも無駄な点灯時間を削減することが難しくなります。これにより、本来削減できるはずの電気代が無駄に消費され続けることになります。
工場の電気代削減方法
工場の電気代削減は、コスト削減だけでなく、企業の持続可能性を高める上でも重要です。ここでは、具体的な削減方法について解説します。
設備機器の効率化
工場内の設備機器の効率を向上させることは、電気代削減の直接的な効果を生みます。
インバーター制御の導入
モーター、ポンプ、ファンなど、様々な設備にインバーターを導入することで、必要な時に必要な分だけ電力を供給し、無駄な電力消費を抑えることができます。これにより、設備の稼働状況に応じた最適な運転が可能となり、特に稼働変動が大きい設備での省エネ効果が期待できます。
高効率モーターへの更新
古いモーターは、最新の高効率モーターに比べて電力消費が大きい傾向にあります。IE3(プレミアム効率)やIE4(スーパープレミアム効率)などの高効率モーターへ更新することで、同じ出力を得るための電力量を削減し、ランニングコストを大幅に削減できます。
コンプレッサーの最適化
工場で多くの電力を消費するコンプレッサーは、エア漏れ対策の徹底や、必要な圧力・流量に応じた適切な制御を行うことが重要です。また、複数台のコンプレッサーを運用している場合は、最適な台数制御や高効率機種への更新を検討することで、無駄な電力消費を抑制できます。
省エネ設備への更新
既存の設備をより省エネ性能の高い設備に更新することは、長期的な電気代削減に繋がります。
LED照明への切り替え
水銀灯や蛍光灯などの従来の照明をLED照明に切り替えることで、消費電力を大幅に削減できます。LED照明は長寿命であるため、交換頻度が減り、メンテナンスコストの削減にも貢献します。人感センサーや照度センサーと組み合わせることで、さらなる節電効果が期待できます。
高効率空調設備への更新
工場で使用される空調設備は、大規模になるほど消費電力が大きくなります。古い空調設備を高効率なGHP(ガスヒートポンプ)やEHP(電気ヒートポンプ)などの最新機種に更新することで、冷暖房効率が向上し、電気代を削減できます。導入時には、補助金制度の活用も検討しましょう。
再生可能エネルギー設備の導入
太陽光発電システムを工場に導入し、自家消費することで、電力会社からの購入電力量を削減できます。余剰電力を売電することも可能ですが、まずは自家消費型で電気代を削減するアプローチが一般的です。蓄電池システムと組み合わせることで、夜間や悪天候時にも自家発電した電力を利用し、ピークカット対策にも繋がります。
運用改善による節電対策
設備更新だけでなく、日々の運用を見直すことでも電気代を削減できます。
デマンド監視とピークカット
デマンド監視システムを導入し、契約電力を超えないように電力使用量をリアルタイムで把握することが重要です。電力需要のピーク時に一部の設備の稼働を一時的に停止したり、シフトを調整したりするピークカットを行うことで、基本料金の削減に繋がります。
空調の適正温度設定とフィルター清掃
空調の冷暖房設定温度を適正に保ち、過度な冷やしすぎや温めすぎを避けることが節電の基本です。また、定期的なフィルター清掃は、空調効率を維持し、無駄な電力消費を防ぎます。
照明の点灯時間と照度の最適化
不必要な照明は消灯し、自然光を最大限に活用しましょう。作業エリアごとに必要な照度を確保しつつ、過剰な明るさを避けることで節電できます。人感センサーや照度センサーの導入も効果的です。
待機電力の削減
使用しない設備や機器は、電源を切るか、コンセントを抜くことで待機電力を削減できます。特に長期休暇前などには、工場全体の電源管理を徹底しましょう。
電力契約の見直し
現在の電力契約が工場の実態に合っているかを見直すことも、電気代削減に繋がる重要な手段です。
契約電力の最適化
契約電力(デマンド値)は、過去1年間の最大使用電力に基づいて決定されます。実際の電力使用量と契約電力に乖離がある場合、契約電力を適正値に見直すことで、基本料金を削減できる可能性があります。ただし、契約電力を下げすぎると、ピーク時にブレーカーが落ちるリスクがあるため、慎重な検討が必要です。
電力会社の比較検討
電力自由化以降、多様な電力会社が様々な料金プランを提供しています。現在の電力会社だけでなく、新電力会社も含めて複数の事業者から見積もりを取り、自社の工場に最適なプランを比較検討することが重要です。使用量や稼働時間帯によって最適なプランは異なるため、詳細なシミュレーションを行いましょう。
高圧・特別高圧契約の見直し
大規模工場で高圧・特別高圧契約を結んでいる場合、契約内容や料金体系が複雑です。専門家のアドバイスを受けながら、契約電力、力率、負荷率などを見直し、自社にとって最も有利な契約形態を検討しましょう。
電力会社の選び方と契約見直し
工場の電気代削減には、日々の節電努力だけでなく、電力会社との契約内容を見直すことも非常に重要です。電力自由化以降、多様な電力会社や料金プランが登場しており、自社の使用状況に最適な契約を選ぶことで、大幅なコストダウンが期待できます。
新電力会社との比較検討
2016年の電力小売全面自由化により、従来の地域電力会社だけでなく、多くの「新電力会社」が工場向けの電力供給サービスを提供しています。新電力会社は、多様な料金プランや付加価値サービス(例:再生可能エネルギー由来の電力供給、CO2排出量削減支援など)を提供しており、企業の環境経営にも貢献する選択肢が増えています。
比較検討の際には、料金単価だけでなく、以下の点にも注目しましょう。
・基本料金と電力量料金の仕組み
・契約期間や解約条件
・供給の安定性や実績
・トラブル発生時のサポート体制
・再生可能エネルギーの導入比率や環境価値
複数の新電力会社から見積もりを取り、自社の電力使用パターンに最も適したプランを選ぶことが、電気代削減の鍵となります。
契約プランの最適化
現在の電力契約が自社の実態に合っているかを見直すことも重要です。特に、デマンド契約を結んでいる工場の場合、契約電力(kW)が実際の最大需要電力(デマンド値)よりも過剰に設定されていると、基本料金を無駄に支払っている可能性があります。過去のデマンド値を詳細に分析し、適切な契約電力に見直すことで、基本料金の削減が期待できます。
また、時間帯別料金や季節別料金プランなど、自社の操業時間や生産スケジュールに合わせた料金プランを選択することも有効です。
例えば、夜間や休日など電力使用量が少ない時間帯に料金が安くなるプランを活用することで、生産計画の見直しと合わせて電気代を抑えることが可能です。電力コンサルタントなどの専門家に相談し、現状の電力使用状況を分析してもらい、最適なプランを提案してもらうことも有効な手段です。
電力切替えなら『アドバンス・キド』の提案する新電力がおすすめ
電力会社の切り替えを検討する際、自社のニーズに合致する特定のサービスプロバイダーを検討することも有効な選択肢です。例えば、コスト削減に特化した料金プランを提供している会社や、再生可能エネルギーの導入を積極的に支援している会社など、多様な選択肢があります。
アドバンス・キドの提案では、シュミレーションで削減効果を確認をしますが、新電力への切り替えで年間最大30%ものコスト削減と安心の電力供給を両立させる可能性があります。そのため、電気代の高騰にお悩みの法人の方にぴったりなサービスとなっております。
①最適なプランをご提案する専門性
お客様の過去1年間の電気使用状況を詳細に分析し、最適な新電力会社・電力プランを厳選します。低圧・高圧問わず対応可能で、シミュレーションにより削減額を明確にした上でご提案。多様な業種で月間23%〜36%の削減実績がある、オーダーメイドの提案力が強みです。
②市場連動型の不安を解消し、安定性を重視
電気料金の変動リスクを抑えるため、安定的な料金設定のプランを扱う新電力会社を厳選。ご要望に応じて固定料金型プランもご紹介可能です。市場データに基づいた詳細なシミュレーションで、変動リスクを分かりやすくご説明し、お客様の納得感を重視した安心できるプラン選択をサポートします。
③経営基盤が安定した「信頼できる新電力会社」のみを厳選
お客様のビジネス基盤を守るため、経営基盤が安定し、長期的な継続供給が可能な信頼性の高い新電力会社のみを厳選しています。大手商社や大手銀行が株主についているなど、財務状況が安定した企業との提携により、お客様は「倒産リスク」の心配なく安心してご利用いただけます。
電気代削減、そして削減したコストの利活用にご興味があれば、まずはお気軽に無料シミュレーションをご依頼ください。貴社の電気代がどれだけ削減できるかをご確認いただけます。
アドバンス・キドの新電力はこちら
https://www.adkd.co.jp/shindenryoku/
新電力に関するご相談・お問い合わせはこちら
https://www.adkd.co.jp/contact/
まとめ:工場での電気代削減を徹底しよう
工場の電気代削減には、まず自社の電力消費状況を正確に把握することが重要です。生産設備や空調、照明などの高負荷要因を特定し、設備効率化や省エネ設備への更新、日々の運用改善を継続的に行うことで、着実にコストを抑えることができます。
特に、複数の新電力会社を比較検討し、自社に最適な契約プランへ見直すことは、電気代を大幅に削減する大きなチャンスです。専門家への相談も視野に入れ、賢く電力コストを削減しましょう。