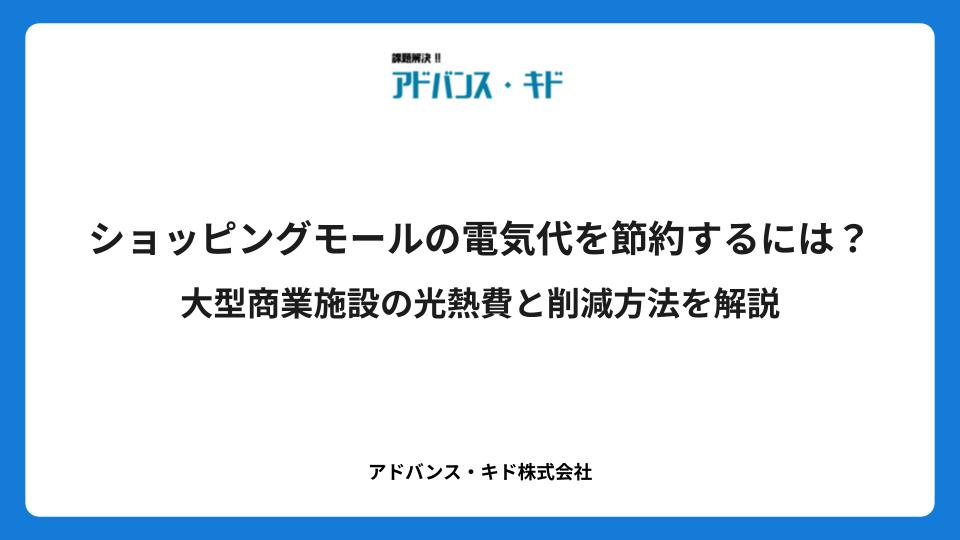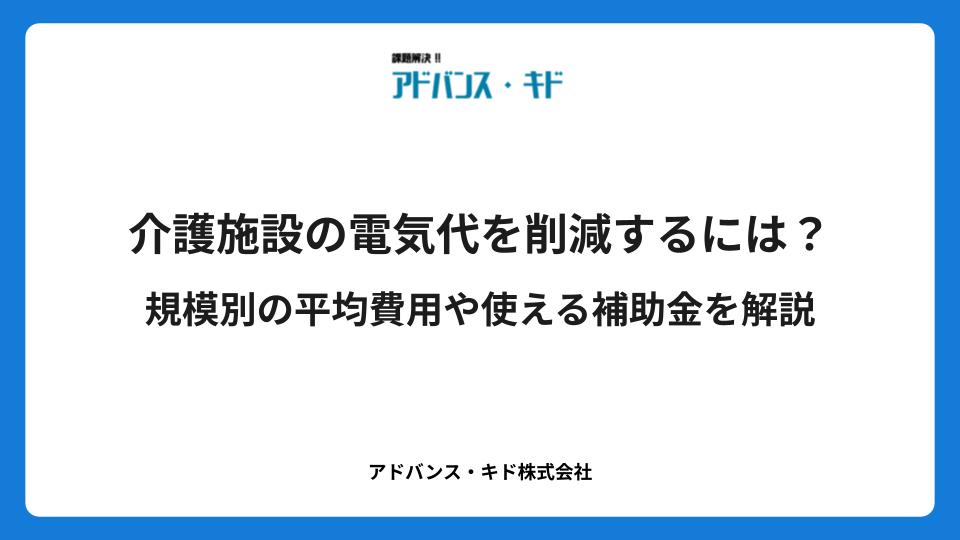記事公開日
高圧と低圧の電気料金の違いは?電気料金の仕組みを基礎から解説

会社の電気料金、なんとなく支払っていませんか?
日々の業務で忙しく、電気料金の明細まで細かく確認できない方も多いのではないでしょうか。しかし、電気の契約には「高圧」と「低圧」という大きな区分があり、電気料金の単価や仕組みが全く異なります。この違いを知らないと、気づかぬうちに損をしているかもしれません。
この記事では、高圧電力と低圧電力の基本的な違いから、自社の契約確認方法、そしてコスト削減のための具体的なステップまで解説します。
1. そもそも高圧電力・低圧電力とは?
まずは、「高圧」と「低圧」がそれぞれどのような契約なのか、基本的な定義から見ていきましょう。この区分は、簡単に言えば「一度にどれくらいの電気を使うか」によって分かれています。
1-1. 高圧電力|工場やオフィスビルなど、多くの電気を使う方向け
高圧電力とは、契約電力が50kW以上2,000kW未満の契約を指します。多くの電気を安定して使用する必要がある、以下のような施設で利用されるのが一般的です。
- 中小規模の工場
- 複数階建てのオフィスビル
- スーパーマーケット
- 病院や学校 など
いわば「電気を大量に使うプロ向けの契約」とイメージすると分かりやすいでしょう。
1-2. 低圧電力|一般家庭や小規模な店舗・事務所向け
一方、低圧電力は契約電力が50kW未満の契約です。私たちの家庭をはじめ、比較的小規模な電気使用量の施設で利用されています。
- 一般家庭
- 個人経営の飲食店や小売店
- 小規模なオフィス・事務所 など
こちらは「一般的な電気契約」であり、ほとんどの方が普段から慣れ親しんでいる契約形態と言えます。
2. 【一覧表で比較】高圧電力と低圧電力、4つの具体的な違い
基本的な対象者が分かったところで、次に「高圧」と「低圧」の具体的な違いを4つのポイントで比較してみましょう。特に電気料金の仕組みの違いは、コスト削減を考える上で非常に重要です。
| 比較項目 | 高圧電力 | 低圧電力 |
|---|---|---|
| ① 電圧 | 6,600V | 100V / 200V |
| ② 電気料金の仕組み | 基本料金(デマンド制)+ 電力量料金 | 基本料金 + 電力量料金(三段階制) |
| ③ 契約電力の決め方 | 過去1年間の最大需要電力(デマンド) | ブレーカーの容量(A) |
| ④ 変圧設備の要不要 | キュービクルが必要 | 不要(電柱の変圧器を利用) |
違い①:電圧の大きさ
最も根本的な違いは、供給される電圧です。低圧が100Vや200Vで直接コンセントに繋がる電圧なのに対し、高圧は6,600Vという非常に高い電圧で供給されます。送電ロスが少ない高電圧で一括受電し、自社で設置した設備(キュービクル)で使える電圧に変圧して使用します。
違い②:電気料金の仕組みと単価
企業にとって最も重要なのが、この電気料金の仕組みと単価の違いです。
- 低圧電力:電気の使用量に応じて料金単価が3段階で高くなる「三段階料金制度」が一般的です。使えば使うほど割高になります。
- 高圧電力:基本料金と電力量料金で構成される点は同じですが、電力量料金の単価が低圧に比べて安価に設定されています。電気を多く使う施設ほど、この単価の安さが大きなメリットになります。
つまり、高圧契約は「大量に仕入れることで単価を安くする」ビジネスの原則と同じと考えることができます。
違い③:契約電力の決定方法
月々の基本料金を決める「契約電力」の算出方法も異なります。
- 低圧電力:設置されているブレーカーの容量(アンペア数)で決まります。
- 高圧電力:「デマンド」と呼ばれる、過去1年間で最も電気を使用した30分間の平均電力によって決定されます。このピーク時の電力が、その後1年間の基本料金を左右するため、デマンドをいかに抑えるかがコスト削減の鍵となります。
違い④:キュービクル(変圧設備)の要・不要
前述の通り、6,600Vの高圧電力を施設内で使える100V/200Vに変換するため、高圧契約の事業所は「キュービクル」と呼ばれる自家用の変圧設備を敷地内に設置する必要があります。この設備の設置や保安点検にはコストがかかりますが、それを補って余りあるほど、高圧電力の料金単価にはメリットがあるのです。
3. 自社の契約はどっち?簡単な見分け方を2ステップで解説
「では、自社の契約は高圧と低圧、どちらなのだろう?」 ここからは、その疑問を解決する具体的な確認方法をご紹介します。
ステップ1:敷地内に「キュービクル」があるか確認する
最も手軽な方法が、自社の敷地や建物の周りを確認し、「キュービクル」を探すことです。
キュービクルは、金属製の箱型の設備で、多くは「高圧危険」といった表示がされています。もしこの設備があれば、貴社は高圧電力を契約している可能性が非常に高いです。
ステップ2:毎月の「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」を確認する
最も確実な方法は、電力会社から毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」を確認することです。検針票の「ご契約種別」という欄に、契約内容が明記されています。
- 高圧電力の例:「業務用電力」「高圧電力」など
- 低圧電力の例:「従量電灯B/C」「低圧電力」など
お手元に検針票があれば、ぜひ一度ご確認ください。
4. 高圧電力契約なら、電気料金はもっと安くなる!「新電力」という選択肢
なぜ高圧電力は「新電力」で安くなるのか?
2016年の電力小売全面自由化により、地域の電力会社だけでなく、様々な「新電力」から電気を買えるようになりました。
特に高圧電力の分野は、それ以前から自由化が進んでいるため競争が活発です。多くの新電力が、大手電力会社よりも割安な料金プランや、企業の特色に合わせたユニークなプランを提供しています。そのため、自社に最適な新電力へ切り替えるだけで、電気の品質はそのままに、料金だけを安くできるのです。
貴社の電気料金削減をプロがサポート
「新電力と言っても、どの会社を選べばいいか分からない」 「手続きが複雑で面倒なのではないか」
このようなご不安を抱える経営者様も多いかと思います。
アドバンス・キドがご提供する「新電力」サービスでは、そのようなお悩みをすべて解決します。 検針票のデータをご提出いただくだけで、貴社に最適な電力会社のプランを専門スタッフが無料でシミュレーションします。削減額にご納得いただいた上で、面倒な切り替え手続きについても最後までフォローさせて頂きます。。
現在の電気の品質や安定供給はそのまま、純粋にコストだけを削減できるチャンスです。
▼まずはお気軽に、無料の料金シミュレーションをお試しください!
アドバンス・キドの新電力サービス 公式サイトはこちら
まとめ:高圧・低圧の違いを正しく理解し、最適な電力契約で経営改善へ
本記事では、高圧電力と低圧電力の違いについて主に解説しました。
電気契約には高圧と低圧があり、料金体系や単価が大きく異なります。工場やオフィスビルなど電気を多く使う施設は高圧契約の可能性が高く、「キュービクルの有無」や「検針票」で確認できます。特に高圧契約の場合、新電力への切り替えが大幅なコスト削減につながることがあります。
物価高騰が続く今、電気料金の見直しは、企業の利益を守り経営を強化する重要な一歩です。この記事を参考に、ぜひ一度、電力契約の見直しを検討してみてください。