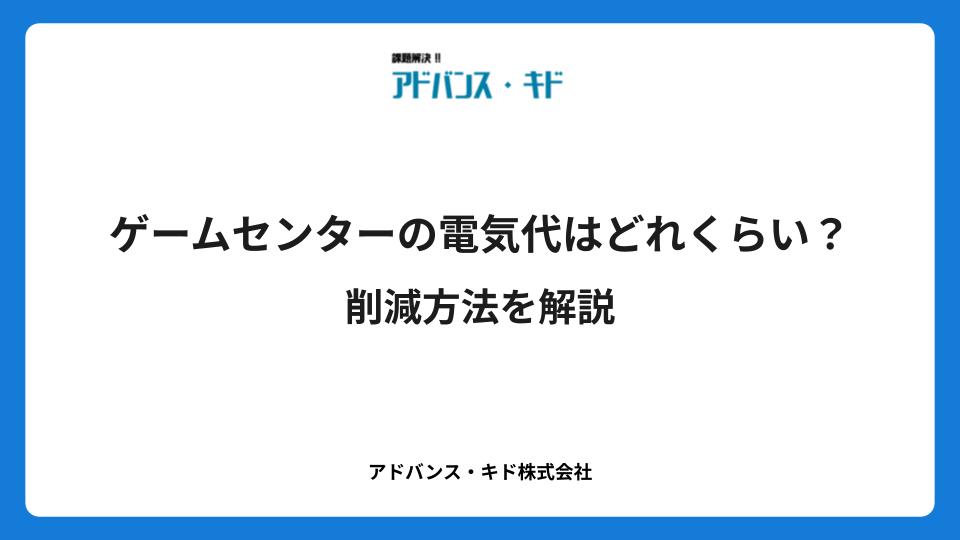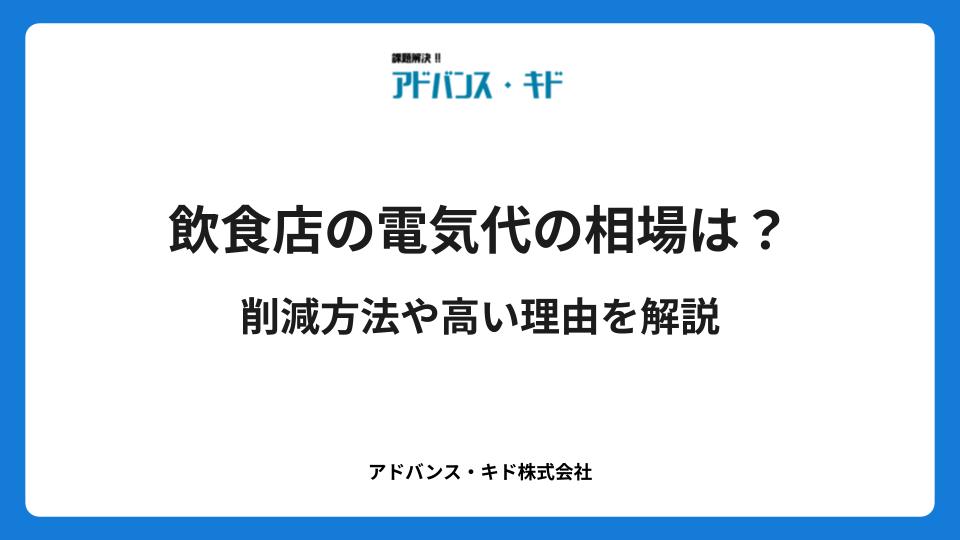記事公開日
学校の電気代は月いくら?節電方法から内訳や特徴も解説
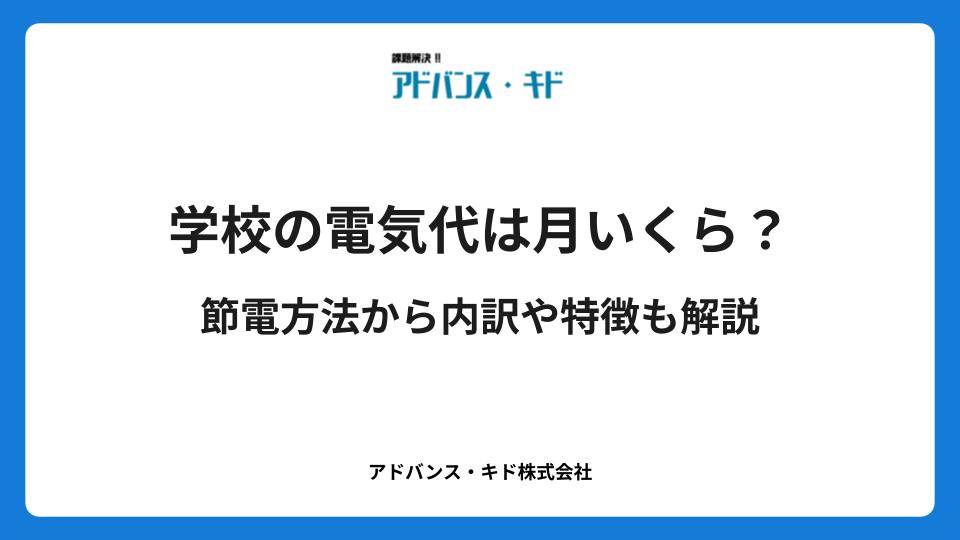
学校運営において、電気代は大きなコストの一つです。特に近年の電気料金高騰により、教育機関の経営を圧迫する要因となっています。
本記事では、学校の電気代の実態から内訳、効果的な節電方法まで解説します。電気代削減は、限られた教育予算を有効活用するための重要な経営課題です。
学校の電気代は月いくらかかる?規模別の平均相場
学校運営において、電気代は光熱水費の中でも大きな割合を占める経費の一つです。その金額は、学校の種類、規模、地域、設備の老朽度、そして日々の運用状況によって大きく変動します。ここでは、一般的な学校における電気代の相場や傾向について、規模別に詳しく見ていきましょう。
小学校の電気代相場
小学校の電気代は、一般的に他の学校種別と比較してやや低い傾向にあります。これは、夜間の利用が少なく、部活動などによる長時間利用が限定的であること、また、特別教室の設備が中学校や高校ほど複雑でないことなどが理由として挙げられます。
しかし、近年ではICT教育の推進により、タブレット端末や電子黒板、校内ネットワークの維持管理にかかる電力消費が増加傾向にあります。
中学校の電気代相場
中学校では、小学校に比べて電気代が増加する傾向が見られます。部活動の活発化により、体育館や武道場、グラウンドのナイター設備などの利用時間が長くなることが一因です。
また、理科室や技術室などの専門教科で使用する機器が増えることや、生徒の成長に伴い空調設備の利用頻度や設定温度への要求が高まることも、電力消費量に影響を与えます。
高校の電気代相場
高校の電気代は、学校種別の中で最も高くなる傾向にあります。これは、中学校以上に部活動が盛んであり、夜間まで施設を利用するケースが多いこと、また、普通科だけでなく、専門学科(工業科、商業科、農業科など)を持つ学校では、その専門設備(実習機械、パソコンルーム、調理室など)の稼働に多大な電力を要するためです。
さらに、受験対策などで夜間自習室を開放する学校もあり、照明や空調の長時間使用が常態化している場合も少なくありません。
私立学校と公立学校の電気代の違い
私立学校と公立学校では、電気代に明確な違いが見られることがあります。一般的に、私立学校の方が公立学校よりも電気代が高くなる傾向があります。これは、私立学校が以下のような特徴を持つことが多いためです。
・最新の冷暖房設備やICT機器、実験設備などを積極的に導入している
・生徒の学習環境や快適性を重視し、冷暖房の利用期間や設定が手厚い
・部活動や課外活動が活発で、施設の利用時間が長い
・セキュリティ対策や防犯カメラ、夜間照明などの設備が充実している
一方、公立学校は予算の制約があるため、設備の更新が遅れたり、節電対策が厳しく求められたりすることが多く、結果として電気代が抑えられる傾向にあります。
しかし、老朽化した設備はかえって電力効率が悪く、長期的に見れば電気代が高くなるケースもあるため、一概には言えません。
学校の電気代が高くなる理由5選
学校の電気代が家計と比べて高額になるのは、その規模と特殊な設備運用に起因します。ここでは、学校の電気代が高くなる主な理由を5つ解説します。
①教室・体育館など広い空間の空調負荷
学校には、教室、職員室、体育館、武道場、多目的ホールなど、広大な空間が多数存在します。これらの空間を快適な室温に保つためには、家庭用とは比較にならないほど大型の空調設備が必要です。
特に夏場の冷房や冬場の暖房は消費電力が大きく、電気代を押し上げる主要な要因となります。また、換気システムの稼働も電力消費に拍車をかけます。
②照明設備の多さと長時間使用
学校は、教室、廊下、階段、体育館、職員室など、建物の隅々にまで多数の照明設備を設置しています。日中の授業時間帯はもちろんのこと、部活動、放課後の補習、夜間開放などで長時間にわたって点灯するケースが多く、これが電気代を高くする一因です。
特に古い校舎では、消費電力の大きい蛍光灯がまだ多く使われている場合があります。
③パソコン教室やサーバー室などのIT機器
近年、GIGAスクール構想の推進により、学校におけるICT(情報通信技術)環境の整備が加速しています。パソコン教室の多数の端末、各教室に導入された電子黒板、生徒一人一台のタブレット端末、そして学校全体のネットワークを支えるサーバー室など、多くのIT機器が稼働しています。
サーバー室は機器の安定稼働と冷却のために24時間空調を稼働させる必要があり、これらのIT機器が消費する電力も電気代に大きく影響します。
④給食室・調理室の厨房設備
給食を提供する学校では、給食室や調理室に大型の厨房設備が導入されています。業務用オーブン、フライヤー、大型冷蔵庫、冷凍庫、食洗機、強力な換気扇などは、家庭用とは比較にならないほどの電力を消費します。
調理時間中はこれらの機器が同時に稼働するため、一時的に大きな電力負荷がかかり、電気代が高くなる要因となります。
⑤プールの循環ポンプと加温設備
学校にプールが設置されている場合、水質を清潔に保つための循環ポンプやろ過装置が常時稼働しています。
さらに、温水プールの場合には、水を適温に保つための加温設備(ヒートポンプやボイラーなど)が莫大な電力を消費します。特に冬季に温水プールを運用する学校では、加温にかかる電気代が非常に高額になる傾向があります。
学校の電気代の内訳
学校の電気代は、一般家庭や企業と同様に複数の要素で構成されています。電気料金明細書には、主に「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の3つの項目が記載されており、これらが学校全体の電力コストを形成しています。学校特有の設備や利用状況が、これらの内訳に大きく影響を与えるのが特徴です。
基本料金
基本料金は、契約している電力の大きさ(契約電力、kW)に応じて毎月固定で発生する費用です。学校の場合、体育館の空調設備や給食室の厨房設備など、一時的に大きな電力を必要とする設備が多いため、契約電力が大きくなりがちです。特にピーク時の最大使用電力(デマンド値)によって契約電力が決まることが多く、このデマンド値が高いと基本料金も高くなります。
電力量料金
電力量料金は、実際に使用した電力量(kWh)に応じて課金される費用です。学校では、教室や体育館の照明、空調、パソコン教室のIT機器、給食室の調理設備、プールの循環ポンプや加温設備など、多岐にわたる施設で電力が消費されます。これらの設備が稼働した総電力量が電力量料金として請求され、使用量が多いほど料金は高くなります。また、契約プランによっては、時間帯や季節によって単価が変動することもあります。
燃料費調整額
燃料費調整額は、火力発電に使用する燃料(原油、LNG、石炭など)の価格変動を電気料金に反映させる仕組みです。燃料価格が上昇すれば電気料金に上乗せされ、下落すれば差し引かれます。この調整額は毎月見直されるため、学校の電気代も燃料価格の動向によって変動します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)の普及を支援するために、電気を使用する全ての消費者が負担する費用です。使用した電力量(kWh)に応じて全国一律の単価が適用され、学校も例外なくこの費用を支払っています。この賦課金は、国の政策に基づいて毎年単価が見直されます。
学校でできる効果的な節電方法10選
1. LED照明への切り替え
学校全体の照明をLEDに切り替えることは、電気代削減に最も効果的な方法の一つです。
LED照明は従来の蛍光灯や白熱灯に比べて消費電力が大幅に少なく、寿命も長いため、交換頻度が減りメンテナンスコストも削減できます。初期投資はかかりますが、長期的に見れば大きなコストメリットが期待できます。
地方自治体によっては、LED化に対する補助金制度を設けている場合もあります。
2. 空調設備の適切な温度設定と管理
教室や体育館などの空調設備は、学校の電気代の大部分を占める要因です。冷房時は室温28℃、暖房時は室温20℃を目安に設定し、過度な冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎましょう。
また、エアコンのフィルターを定期的に清掃することで、運転効率が向上し、無駄な電力消費を抑えられます。室外機周辺に物を置かない、直射日光を避けるなどの工夫も有効です。
3. 人感センサーや自動消灯システムの導入
誰もいない教室や廊下、トイレなどで照明が点きっぱなしになるのを防ぐため、人感センサーや自動消灯システムを導入することは非常に効果的です。これにより、消し忘れによる無駄な電力消費を自動的に削減できます。タイマー設定を活用し、授業時間外や夜間は自動で照明を落とすといった運用も検討しましょう。
4. 窓ガラスの遮熱・断熱対策
窓ガラスから出入りする熱は、空調効率に大きく影響します。遮熱フィルムを貼る、二重窓にする、厚手の遮光・遮熱カーテンを設置するなどの対策により、夏場の冷房負荷を軽減し、冬場の暖房効果を高めることができます。
これにより、空調設備の運転時間を短縮し、電気代の削減につながります。
5. デマンド監視システムの活用
学校の電気料金は、基本料金と電力量料金で構成されており、基本料金はピーク時の電力使用量(デマンド値)に基づいて決定されます。
デマンド監視システムを導入することで、リアルタイムの電力使用状況を把握し、デマンド値が設定値に近づいた際にアラートを出すことが可能です。これにより、一時的に消費電力の大きい機器の使用を控えるなど、ピークカット対策を行い、基本料金の削減を目指せます。
6. 省エネ型空調設備への更新
長年使用している古い空調設備は、最新の省エネ型設備に比べて消費電力が大きい傾向があります。
特に老朽化した空調設備は故障のリスクも高まるため、計画的に高効率なインバーター式エアコンやガスヒートポンプ(GHP)などの省エネ型設備への更新を検討しましょう。初期費用はかかりますが、長期的な電気代削減効果と快適性の向上に寄与します。
7. 太陽光発電設備の導入検討
学校の屋根や敷地に太陽光発電設備を導入することで、自家消費による電気代削減が期待できます。発電した電気を学校内で使用すれば、電力会社から購入する電力量を減らせます。
また、余剰電力を売電することも可能です。災害時には非常用電源としても活用できるため、BCP(事業継続計画)の観点からもメリットがあります。
8. 電気機器の待機電力削減
パソコン、コピー機、充電器など、多くの電気機器は使用していなくてもコンセントに繋がっているだけで待機電力を消費しています。
授業終了後や長期休暇中は、不要な電気機器の主電源を切り、コンセントからプラグを抜くことを徹底しましょう。一括で電源を管理できるOAタップの導入も有効です。
9. 教職員・生徒への節電意識の啓発
設備投資だけでなく、日々の運用における意識改革も重要です。教職員や生徒に対し、節電の重要性や具体的な方法を周知徹底しましょう。
ポスター掲示、校内放送、朝礼での呼びかけ、授業での環境教育などを通じて、一人ひとりが節電を意識し、実践する文化を醸成することが長期的な電気代削減につながります。
10. 電力使用状況の定期的な見える化
学校全体の電力使用量を定期的に集計し、グラフなどで「見える化」することで、節電効果を実感しやすくなります。各教室や部署ごとの電力消費量を比較したり、前年同月比で削減目標を設定したりすることで、節電活動へのモチベーションを高めることができます。
データに基づいて課題を特定し、改善策を検討するPDCAサイクルを回しましょう。
学校の電気代削減に効果的な電力会社の見直し
電力自由化以降、学校も自由に電力会社を選べるようになりました。従来の地域電力会社だけでなく、新電力会社との契約は、電気代削減の大きな鍵となります。学校の特性に合わせた最適な電力プランを選ぶことで、大幅なコスト削減が期待できます。
新電力への切り替えで期待できる削減効果
新電力会社は、多様な料金プランを提供しており、学校の電力使用状況に合わせた最適なプランを選択できます。
例えば、基本料金や電力量料金の単価が地域電力会社よりも安価に設定されているケースが多く見られます。また、再生可能エネルギー由来の電力を選択できるプランもあり、電気代削減だけでなく、CO2排出量削減といった環境貢献にも繋がります。
学校の年間電力使用量や時間帯別の使用パターンを分析することで、ピーク時のデマンド抑制に貢献するプランや、夜間や休日割引のあるプランなど、学校運営に即したメリットを享受できる可能性があります。これにより、固定費である電気代を効率的に削減し、予算を他の教育活動に充てることが可能になります。
学校に適した電力プランの選び方
学校に適した電力プランを選ぶためには、まず自校の年間電力使用量、季節ごとの変動、時間帯別の使用パターン、そして最大デマンド値を正確に把握することが重要です。これらのデータに基づき、複数の新電力会社から見積もりを取り、以下の点を比較検討しましょう。
| 料金体系 | 基本料金、電力量料金(従量料金)、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金など、各項目の単価や計算方法。 |
|---|---|
| 契約期間と解約条件 | 中途解約時の違約金など、契約期間中の制約を確認。 |
| 電源構成 | 再生可能エネルギーの比率など、環境への配慮を重視するかどうか。 |
| 実績 | 他の学校や公共施設への導入実績があるか。 |
学校の規模や設備(プール、給食室、IT機器の多さなど)によって最適なプランは異なります。例えば、体育館やプールの利用で一時的に電力消費が跳ね上がる学校では、デマンド監視やピークカットに強いプランが有効です。複数の選択肢を比較検討し、最もコストパフォーマンスが高く、安定供給が期待できるプランを選定することが重要です。
新電力への切り替えならアドバンス・キドがおすすめ
学校の電気代削減を検討されている場合、新電力への切り替えは非常に有効な選択肢です。特に、学校の電力消費特性を深く理解し、最適な料金プランを提案する実績を持つ電力会社を選ぶことが重要です。
例えば、アドバンス・キドのような学校が使用する電気の特性を理解したうえで、サービスを提供する電力会社であれば、単に電気を供給するだけでなく、省エネコンサルティングや再生可能エネルギー導入支援など、総合的なサポートを提供している場合があります。
切り替え手続きの簡素さや、導入後の安定したサポート体制も選定の重要なポイントとなります。学校運営に支障をきたすことなく、スムーズに移行できるよう、実績と信頼のある電力会社を選ぶことで、長期的な視点での電気代削減と環境負荷低減を実現できるでしょう。
まとめ:学校の電気代削減は経営改善の第一歩
本記事でご紹介したように、学校の電気代削減は、単なる経費削減以上の意味を持ちます。それは、限られた予算を子どもたちの教育環境の充実という、本来あるべき姿に再分配するための重要な経営戦略です。しかし、「どの電力会社が信頼できるのか」「公的な施設として最適な選択は何か」といった判断は、決して簡単なことではありません。
私たちアドバンス・キドは、学校という公共性の高い施設の特性を深く理解し、電力の安定供給を大前提として、経営基盤の強固な新電力会社のみを厳選いたします。
貴校の電力使用データをプロの視点で詳細に分析し、教育活動に最適な料金プランを無料でご提案。削減できた予算を、ICT教育の推進や教材の購入、施設の改修といった未来への投資に繋げるお手伝いをいたします。
大切な教育予算を最大限に活かすためのパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。