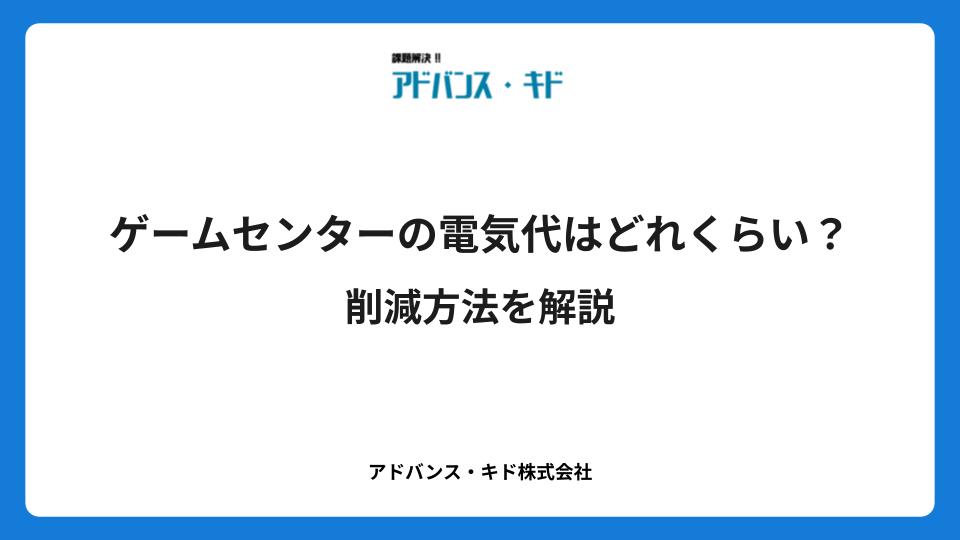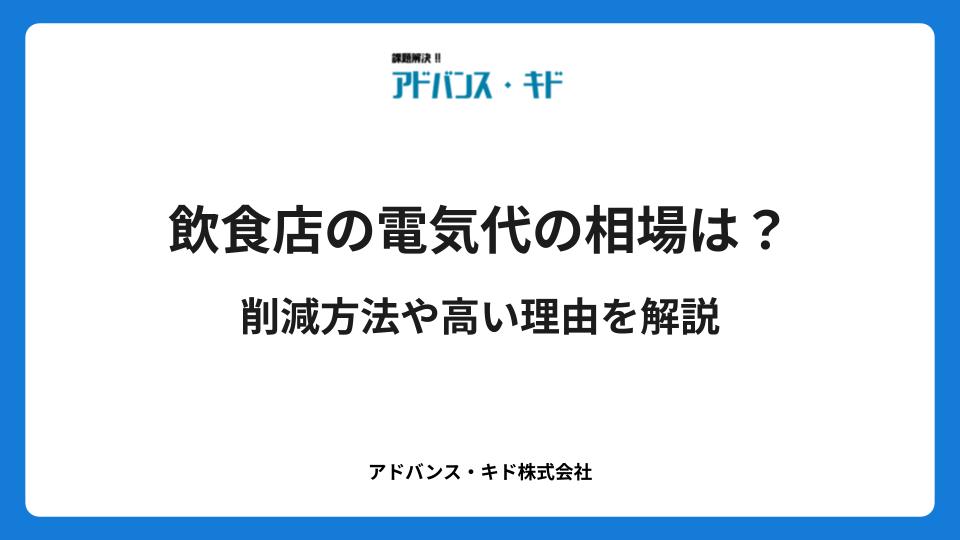記事公開日
病院の電気代、どう削減する?相場や実態なども解説
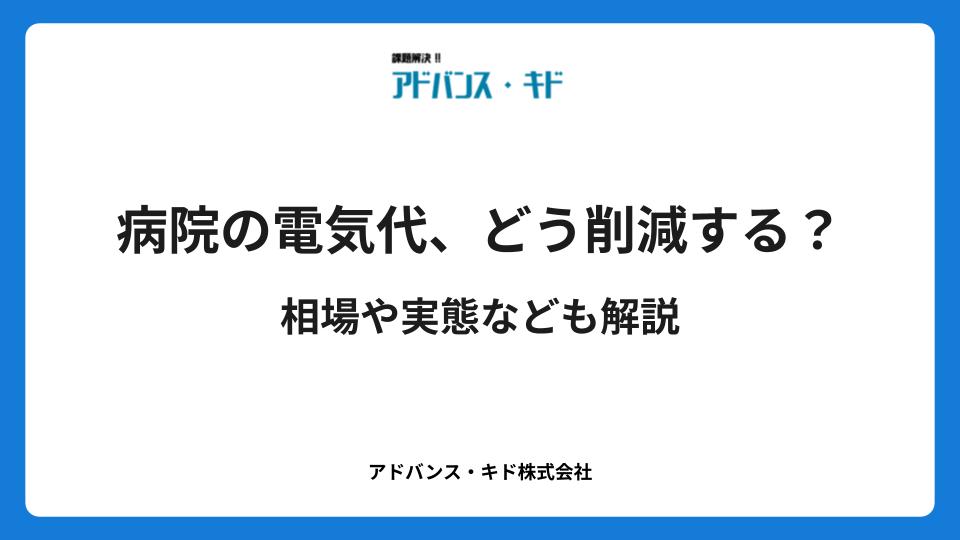
24時間365日稼働が求められる病院では、電気代が経営を圧迫する大きな課題となっています。医療機器の多用、空調設備の常時運転、夜間照明など、一般企業とは異なる電力需要があり、「電気代をどう削減すればよいのか」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、病院の電気代の実態や相場を明らかにしたうえで、具体的な削減方法を解説します。
病院の電気代の実態と相場
病院の電気使用量の特徴
病院の電気使用量は、他の一般企業や施設と比較して非常に特殊な特徴を持っています。
まず、患者さんの命に関わる医療サービスを24時間体制で提供するため、医療機器、照明、空調などの主要設備が常時稼働している点が挙げられます。特に、MRIやCTスキャンといった高度な診断機器、手術室の精密機器、集中治療室(ICU)の生命維持装置などは、非常に大きな電力を消費します。
また、衛生管理の徹底が求められるため、給湯設備や滅菌器も頻繁に使用され、これらも多量の電力を必要とします。
さらに、患者さんや医療従事者の快適性を維持するための空調設備も、広範囲にわたり長時間稼働することが特徴です。これらの要因が複合的に作用し、病院全体の電気使用量を押し上げています。
病院の平均的な電気代相場
病院の電気代相場は、病床数、診療科の種類、建物の規模、築年数、地域、そして契約している電力会社やプランによって大きく変動します。そのため、一概に「平均的な電気代」を示すことは困難ですが、一般的に数百万から数千万円、大規模な病院では億単位の電気代が毎月発生することもあります。
多くの病院では、電力会社と高圧電力または特別高圧電力で契約しており、使用量に応じた基本料金と電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金などで構成されます。
一般企業との電気代比較
病院の電気代は、オフィスビルや工場といった一般企業と比較しても高額になる傾向があります。この主な理由は、前述の電気使用量の特徴に起因します。
一般企業が主に日中の稼働であるのに対し、病院は24時間365日稼働が基本です。また、オフィスビルでは照明や空調が主な電力消費源ですが、病院ではこれに加えて、高出力かつ精密な医療機器の常時稼働が必須となります。
さらに、感染症対策のための換気システムや、手術器具の滅菌、患者さんの入浴や清拭に使う大量の給湯設備など、医療固有の電力消費要素が多数存在します。これらの特殊な電力需要が、一般企業とは一線を画す高い電気代へとつながっています。
病院で電気代が高くなる主な要因
病院の電気代が高額になる背景には、その特殊な運営形態と医療サービスの提供に不可欠な設備が大きく関係しています。一般のオフィスビルや工場とは異なる、病院ならではの要因について解説します。
医療機器による電力消費
病院には、患者の診断や治療に不可欠な高度な医療機器が多数導入されています。例えば、MRI(磁気共鳴画像診断装置)やCT(コンピュータ断層撮影装置)は、一度の検査で大量の電力を消費します。
また、手術室で使用される各種機器、ICU(集中治療室)やCCU(冠疾患集中治療室)で24時間稼働する人工呼吸器や生体モニターなども、安定した電力供給を必要とし、全体の電力消費量を押し上げる要因となります。
空調設備の常時稼働
病院では、患者さんの快適性や医療機器の安定稼働、そして感染症対策のために、年間を通して広範囲で空調設備を常時稼働させる必要があります。
特に手術室やICU、無菌室などでは、厳密な温度・湿度管理が求められるため、高性能な空調システムが24時間体制で稼働しており、これが大きな電力消費に繋がります。大規模な病院ほど、空調対象となる面積が広がり、消費電力も増加する傾向にあります。
24時間照明・設備稼働
病院は24時間体制で患者さんの受け入れや治療を行うため、夜間も多くの場所で照明を点灯し、様々な設備を稼働させています。病室、廊下、ナースステーション、受付、手術室、検査室など、患者さんやスタッフの安全確保、業務遂行のために欠かせない照明は、広範囲にわたるため積算すると大きな電力消費となります。
また、エレベーター、給水ポンプ、セキュリティシステムなども常時稼働に近い状態で、病院全体の電力消費量を増加させています。
給湯・滅菌設備の電力消費
病院では、患者さんの入浴、手洗い、清掃、調理などに大量の温水が必要となるため、給湯設備が大きな電力を消費します。特に冬場は、給湯需要が高まり、消費電力も増加します。
さらに、手術器具や医療用品の感染症対策として行われる滅菌処理には、高圧蒸気滅菌器やEOG(エチレンオキサイドガス)滅菌器などが使用されます。これらの滅菌設備は、高温を維持するために多くの電力が必要であり、病院の運営上欠かせないプロセスであるため、電気代が高くなる要因の一つとなっています。
病院の電気代削減方法5選
①電力使用状況の可視化
病院の電気代削減の第一歩は、現在の電力使用状況を正確に把握することです。スマートメーターやBEMS(ビルディング・エネルギー管理システム)を導入することで、時間帯別や機器別の電力消費量をリアルタイムで可視化できます。
これにより、どの時間帯に、どの設備が、どれくらいの電力を消費しているのかが明確になり、無駄な電力消費を発見しやすくなります。例えば、夜間や休診日に稼働している不要な機器がないか、ピーク時間帯に電力を集中させている要因は何かなどをデータに基づいて分析し、具体的な改善策を検討するための基礎情報となります。
②ピーク電力の抑制
病院の電気料金は、使用した電力量(電力量料金)だけでなく、契約電力(基本料金)にも大きく左右されます。契約電力は、過去1年間で最も多く使用した30分間の平均電力(最大需要電力、デマンド値)に基づいて決定されることが多いため、このピーク電力を抑制することが電気代削減に直結します。
デマンド監視システムを導入し、設定したデマンド値を超えそうになった際にアラートを発する仕組みを構築することで、不要な機器の停止や稼働時間の調整を行う「ピークカット」が可能です。また、蓄電池を導入して電力需要の低い時間帯に充電し、ピーク時に放電する「ピークシフト」も有効な手段です。これらの対策により、基本料金の大幅な削減が期待できます。
③照明のLED化
病院内の照明は、24時間稼働している場所も多く、消費電力の大きな割合を占めます。従来の蛍光灯や白熱灯をLED照明に切り替えることは、電気代削減に非常に効果的です。
LED照明は、従来の照明に比べて消費電力が大幅に少なく、寿命も長いため、交換頻度が減りメンテナンスコストも削減できます。初期投資はかかりますが、長期的に見れば確実に電気代を抑えることができます。また、人感センサー付きのLED照明や、時間帯に応じて明るさを調整できる調光システムを導入することで、さらにきめ細やかな節電が可能になります。
④空調設備の運用改善
病院の空調設備は、患者さんの快適性や医療機器の安定稼働のために常時稼働していることが多く、電気代の主要な要因の一つです。空調設備の運用改善は、大きな削減効果を生み出します。
まず、設定温度の適正化が重要です。過度な冷暖房を避け、夏は少し高め、冬は少し低めに設定するだけでも消費電力は大きく変わります。
また、フィルターの定期的な清掃は、空調効率を維持し、無駄な電力消費を防ぐために不可欠です。古くなった空調設備は、最新の高効率モデルに更新することで、大幅な省エネ効果が期待できます。
⑤新電力への切り替え
2016年の電力小売全面自由化以降、病院のような高圧・特別高圧の契約をしている事業者も、既存の電力会社だけでなく、多くの新電力会社から自由に電力供給元を選べるようになりました。
新電力会社は、多様な料金プランやサービスを提供しており、病院の電力使用状況に合わせた最適なプランを選ぶことで、電気代を削減できる可能性があります。
例えば、特定の時間帯の料金が安くなるプランや、再生可能エネルギー由来の電力を提供するプランなどがあります。新電力に切り替えても、送電網はこれまでと同じものが使用されるため、電力の安定供給や品質に影響が出ることはありません。
複数の新電力会社から見積もりを取り、比較検討することで、現在の契約よりも安い料金で電力を調達できる可能性が高まります。
新電力への切り替えならアドバンス・キドがおすすめ
病院経営において、電気代の削減は重要な課題の一つです。数ある新電力会社の中でも、アドバンス・キドは病院が抱える特有の電力事情を深く理解し、最適なソリューションを提供しています。
医療機関では、24時間体制での稼働や、精密な医療機器の安定稼働が不可欠です。アドバンス・キドは、単なるコスト削減だけでなく、電力の安定供給を最優先に考えたサービス設計を強みとしています。万が一の事態にも備えた供給体制を整え、病院の運営に支障が出ないよう配慮しています。
また、専門のコンサルタントが各病院の電力使用状況を詳細に分析し、個々の施設に合わせたオーダーメイドの削減プランを提案します。現在の電力契約内容や使用パターンを精査し、無駄をなくすための具体的な施策を立案することで、より効果的な電気代削減を実現します。
新電力への切り替え手続きも、アドバンス・キドが全面的にサポートするため、病院側の負担は最小限に抑えられます。煩雑な手続きに時間を割くことなく、スムーズに切り替えを進めることが可能です。
アドバンス・キドの新電力はこちら
新電力に関するご相談・お問い合わせはこちら
新電力への切り替えでよくある質問
Q1. 新電力に切り替えても医療機器への影響はないか?
新電力に切り替えても、医療機器の動作や病院の電力供給の安定性には影響ありません。電気はこれまで通り、地域の大手電力会社(一般送配電事業者)が管理する送配電網を通じて供給されます。新電力会社は電気の調達と料金設定を行うだけであり、電力の品質や安定供給の責任は変わりません。
Q2. 切り替えに費用はかかるのか?
基本的に、新電力への切り替えに初期費用はかからないケースがほとんどです。スマートメーターが設置されていない場合は、電力会社が無料で設置工事を行います。ただし、現在の電力会社との契約内容によっては、解約時に違約金が発生する場合がありますので、事前に確認が必要です。
Q3. 契約期間の縛りはあるのか?
新電力会社によって契約期間の条件は異なります。一般的には1年から3年程度の契約期間が設定されていることが多いです。契約期間中に解約した場合、違約金が発生するプランもありますので、契約前に必ず確認するようにしましょう。
Q4. 停電リスクは高まらないか?
新電力への切り替えによって停電リスクが高まることはありません。電力の供給を担う送配電網は、これまでと変わらず地域の大手電力会社(一般送配電事業者)が管理・保守しています。新電力会社が倒産した場合でも、電気の供給が突然停止することはなく、別の電力会社に切り替えるまでの間は、大手電力会社から電気が供給される仕組みになっています。
Q5. どのくらいの期間で削減効果が出るのか?
新電力への切り替えによる電気代削減効果は、切り替え後の最初の検針期間から現れます。具体的な削減額は、契約する新電力会社のプランや病院の電力使用状況によって異なりますが、通常は数ヶ月でその効果を実感できることが多いです。長期的な視点で見れば、年間で大きな削減につながる可能性があります。
まとめ:病院の電気代削減は経営改善の第一歩
病院の電気代は、医療機器の常時稼働や24時間体制の運営により、経営を圧迫する大きな要因です。しかし、電気代削減は単なるコストカットに留まらず、経営体質を強化し、持続可能な病院運営を実現するための重要な経営改善策となります。
本記事でご紹介した「電力使用状況の可視化」や「ピーク電力の抑制」、そして「新電力への切り替え」といった具体的な方法を実践することで、確実に電気代を削減できます。特に、信頼できる新電力への切り替えは、手間なく大きな削減効果が期待でき、病院経営の健全化に大きく貢献するでしょう。この一歩が、患者様へのより良い医療提供に繋がります。