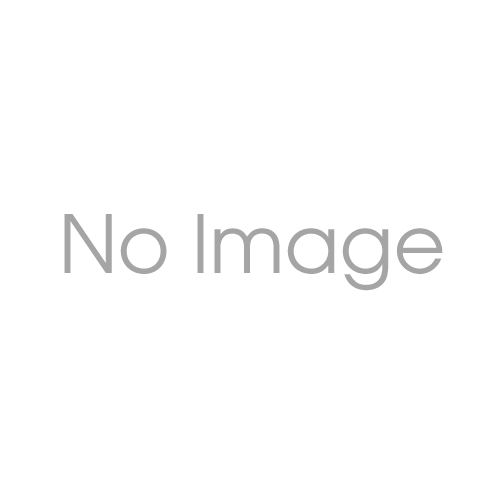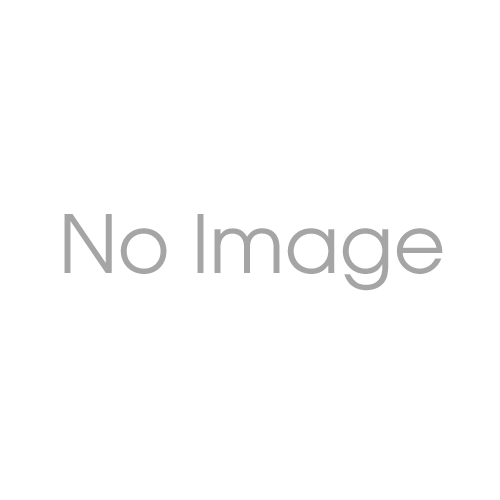記事公開日
風力発電の状況について
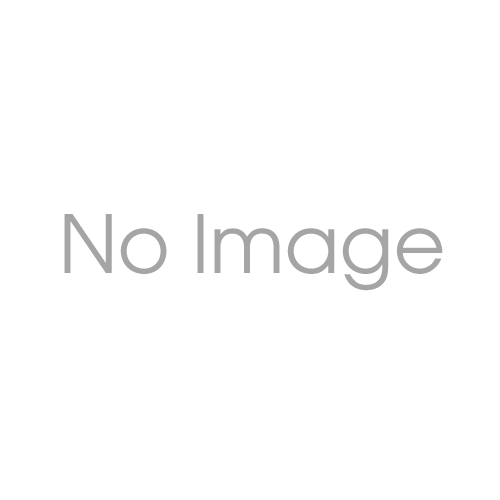
2025年10月6日の日本経済新聞に「風力 三菱商事ショック」「GEもアマゾンも断った」というタイトルの記事が掲載されてました。記事の内容は、2021年12月に「政府によるに洋上風力の大規模入札で、三菱商事が秋田県沖を含む3海域を総取り」した件です。2024年秋、風車納入契約の期限を迎えた中でアメリカのGEベルノバよりインフレで資材が高騰し条件面で納入できなくなったと三菱商事に連絡がありました。三菱商事は慌てて、ドイツのシーメンス、デンマークのベスタスとも交渉しましたが、入札で約束した売電価格での条件では折り合いがつきませんでした。また、アマゾンジャパンやグーグルに電気の購入を約束して頂く交渉も「数年先の運転開始の案件で高額な電力購入はできない」と断られました。そのため、三菱商事は、やむを得ない結論として、経済産業省に撤退の報告をしたとのことでした。私は日立製作所で公共担当だったので、三菱商事が厳しい判断を下したことがよくわかります。一般的に、落札した案件の撤退は、その後の入札案件で指名停止となり、入札に参加できなくなります。あとあとのビジネスチャンスを逃すことになるので、普通は落札した会社としては、是が非でも落札金額内、決められた納期内での納入を死守します。三菱商事は、そのような結果を承知の上で、撤退の判断をしたと思います。ただ、もし、三菱グループの三菱重工業が風力発電の製造から撤退していなかったら、違った展開になっていたかもしれません。三菱重工業は、長崎で大きなブレードの風車を製造してました。2014年に自社製造を中止し、デンマークのベスタス社の風力発電を販売することにしました。私の古巣の日立製作所もスバル風車という素晴らしい風力発電を製造してましたが、2019年に製造から撤退し、ドイツのエネルコン社の風力発電を販売することにしました。つまり、現段階で日本では1社も風力発電を製造していません。今回の三菱商事の原価低減できなかった原因のひとつに国内で製造していたメーカーがなかったことがあげられると私は思ってます。やはり、国内で作らないと、材料費の対応だけでなく、保守も含めたライフサイクルコストも考えて、原価低減をしないと難しいと思います。
今回は、日本における風力発電の状況について話します。
目次
- 風力発電の状況について
- 日本における風力発電の状況について
- 今後の風力発電について
- 中小企業の対応について
- アドバンス・キド株式会社からのご提案
- 風力発電の状況について
風力発電とは、風のエネルギーを利用して発電する仕組みです。風力発電では、風の力で風車のブレードを回転させます。ブレードの回転を風車内の機械室(ナセル)内にある増速機で増やし、発電機で電気に変換し発電しています。陸上風力発電は、風車を陸上に設置して発電する方式です。風力発電は一定以上の風速と安定した風向が必要なため、風車は主に山岳部や海岸沿いに設置されます。風車の形により、水平軸式(プロペラ型、オランダ型など)と垂直軸式(サヴォニウス型、ダリウス型など)に分けられます。
陸上風力発電はコストを抑えやすい特徴があるため、日本でも複数の地域で導入されている発電方法です。一方で、風向きにより発電が不安定になる、騒音や景観の問題があるなどの課題が残されています。
洋上風力発電は、風車を洋上(海・湖など)に設置して発電する方法です。風車を支える構造物によって、着床式洋上風力発電と浮体式洋上風力発電に分類されます。洋上風力発電は、陸上と比較して風況が安定しやすく、効率的な発電が可能です。船舶による機材の運搬が可能で、大型の風車を導入しやすいメリットを持ちます。しかし、洋上風力発電は基礎工事の難しさ、建設費や維持管理費のコストが課題です。
世界の風力エネルギーは過去10年間で飛躍的な進歩を遂げ、クリーンで手頃な価格、そして安全なエネルギーを確保するための最も効果的な再生可能エネルギーソリューションの一つとしての地位を確立しました。道のりは多くの課題に満ちていますが、国際協力、技術革新、そして政治的コミットメントによって風力発電容量の拡大が推進され続け、エネルギーモデルを変革し、より持続可能な未来に貢献する新たな機会が生まれています。世界の風力発電は2024年に記録的なレベルに達し、世界の脱炭素化の鍵となってます。新たな風力発電設備の導入は中国と欧州が主導しています。風力発電をエネルギーミックスに統合することを加速するには、政治的安定やイノベーションなどの要素が不可欠です。風力エネルギー分野はリサイクルなどの課題に直面していますが、持続可能性と循環型経済に向けて前進し続けています。
- 日本における風力発電の状況について
風力発電は再生可能エネルギーのひとつとして期待されていますが、日本は欧米諸国と比較すると、普及の途上にある状況です。
一般社団法人日本風力発電協会(JWPA)は2024年12月末時点における日本国内の風力発電導入実績を取りまとめました。2024年の新規導入量は、全国23サイトで703.3MW(170基)となりました。一方、撤去したサイトを差し引いた正味導入量(Net)は、15サイトで663.0MW(120基)となり、結果として累積導入量は5,840.4MW(2,720基)に達しました。特に洋上風力においては、石狩湾新港洋上風力発電所が運転を開始し、新たな大型案件として導入量の増加に寄与しました。これにより、2023年に稼働した秋田港洋上風力発電所や入善洋上風力発電所に続き、日本の洋上風力市場はさらに拡大しています。また、地域別では北海道地区での導入量が前年比約455MW増加し、全国一位となりました。さらに、風車の単機容量は引き続き大型化が進んでいます。
3.今後の風力発電について
日本の風力発電に関する研究・開発は進んでいますが、世界と比較するとまだ発電コストが高い傾向にある点が課題です。2021年上半期における世界の陸上風力発電のコストは、4.5円/kWhです。同期間の日本の陸上風力発電コストは11.8円/kWhであり、約2.6倍の差が存在します。風力発電を今以上に普及させるためには、より一層のコスト低減が必要です。
また、2022年の風車メーカーのシェアは、上位を中国やヨーロッパなど海外のメーカーが占めています。国内では風力発電の市場の成長が遅れたこともあり、風車の調達を海外に依存する部分が大きいです。風車調達の海外依存は、風車の供給不足や円安の影響によるコストの増加につながっています。日本は海に囲まれた地理的条件から、洋上風力発電の大きなポテンシャルを持つといわれています。日本は、急速に風力発電供給量を伸ばしたイギリスと比較すると、排他的経済水域が広く、広範囲にわたる海岸線を持つ点で共通しています。今後の技術開発や実用化に向けた研究により、日本は風力発電の分野で大きな可能性を秘めていると考えられます。
欧州レベルでは、2030年までに毎年数千基の風力タービンが解体されることが予想されています。施設の改修や耐用年数の終了に伴い、風力発電設備の老朽化が進んでいます。この課題に対処し、風力発電産業の競争力を維持するには、リサイクル技術の進歩と官民連携が鍵となります。
世界の風力発電容量に関する将来の課題の 1 つは、風力タービンのコンポーネントの持続可能な管理です。特に使用済みブレードのリサイクルが盛んに行われています。スペイン・ナバラ州に開設されたEnergyLOOP工場のような事例は、このセクターが循環型経済に注力していることを示しており、材料のリサイクルと他の産業分野での再利用を促進しています。
4.中小企業の対応について
風力発電は、設置した地域経済への貢献が期待されています。風力発電施設の建設のために投資された建設費用や雇用費用の直接的な経済波及効果は、その一例です。風力発電の維持管理に必要な部品や人材で需要が生まれれば、地元の部品メーカーや施工業者に継続的な経済効果が期待できます。その他、風力発電所建設のための不動産取得税、その後の固定資産税や法人事業税などにより、地元自治体の税収効果が見込めます。風力発電はエネルギー産出への貢献だけでなく、地域の活性化にもつながる施策です。
また、風力発電の普及には、開発やメンテナンスに関わる人材育成が重要です。たとえば長崎大学では、秋田大学や三菱商事株式会社と産学連携し、洋上風力発電の事業開発に必要な人材育成カリキュラムの策定を行っています。2024年4月からは、秋田県男鹿市の「風と海の学校 あきた」、茨城県神栖市の「ウィンド・パワー・トレーニングセンター」などのトレーニング施設がオープンしました。風力発電の普及を拡大するべく、様々な分野で取り組みが進んでいます。
日本の風力発電は、現状、電力構成の約0.9%を占めるにとどまっています。山地の多い日本の地形や発電コストの高さが課題です。一方、周囲を海に囲まれた日本は、洋上風力発電の高いポテンシャルを持っています。政府や企業の取り組みにより、今後さらなる導入が見込まれる分野です。
5.アドバンス・キド株式会社からのご提案
風力発電を活用して、街づくりをするのはいかがでしょうか。発電した電力は、街で活用することを前提に設置をしたらいかがでしょうか。電気代が高騰している状況で、電気代は街が負担するという仕組みを、大体的に発表すれば、手に職を持った技術者や企業がその街にくると思います。地元の業者も活性化すると思います。街または区域の有志が主導して、プロジェクトを進めると、活動スケジュールが活きてきます。自分たちで地域の住民を巻き込んで取り組むのが大事だと思います。私の古巣の日立製作所が生産を中止したスバル風車のブレードは、スバルの前の会社である中島飛行機で培った技術が入ってました。これをそのまま忘れ去られるのは惜しい技術です。日本で今一度、風力発電を作り、祖先が残した技術を継承しまたは復活し、子孫に伝えていきましょう。
今回の三菱商事が落札したのに撤退を表明した背景には、日本でモノをつくっていない弱さをマザマザと見せ付けられたと思います。簡単なことではないですが、街の皆さんが協力し合って風車を作って、街の電力に自分たちで消費しましょう。
まずは、電気代の見直しをして、資金に余裕を作り、各々の会社が情報化を推進していくことが大事です。会社の体力をつけて、地域の活性化を実施し、徐々に周りに元気を拡げていきましょう。
以 上