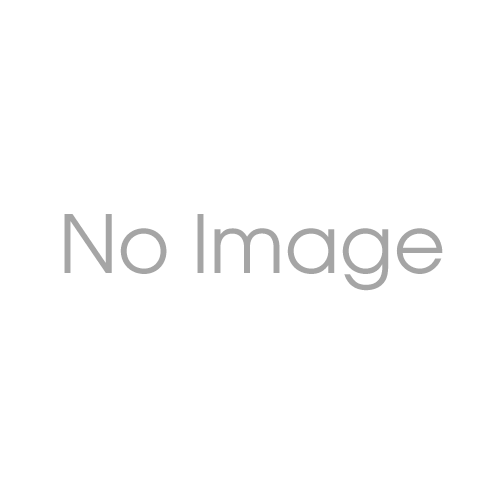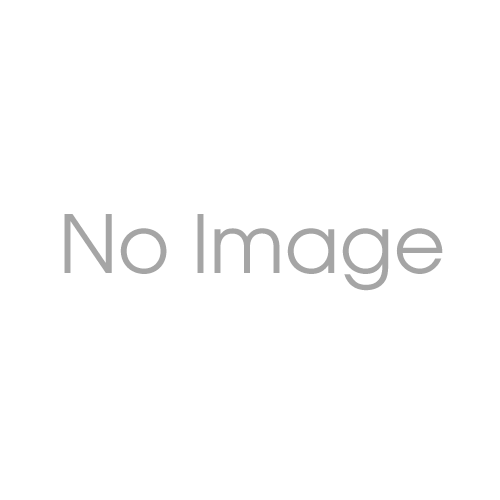記事公開日
自動運転バスについて
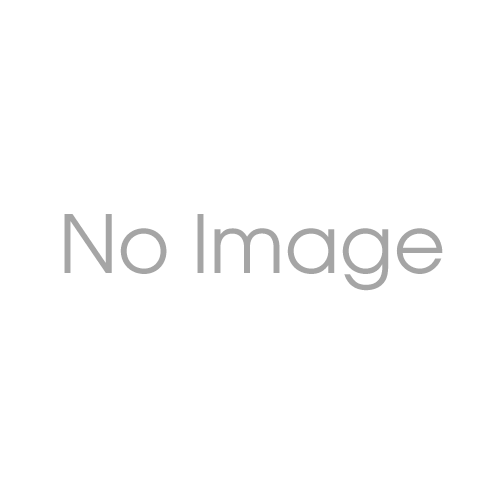
2025年10月18日の日本経済新聞に「自動運転バス 街の足に」「運転手不足埋める 万博で体験も」「走行台数2年で5倍」というタイトルの記事が掲載されてました。また、日本軽罪新聞の九州地域の記事で「レベル4実現へアクセル」「沖縄・豊見城。自動運転バス実証」「中心市街地で来年度目標」というタイトルの記事が掲載されてました。どちらも「自動運転バス」についてです。記事の内容は、運転手不足を背景に路線バスの廃止が相次ぐ中、住民の足を支える手段として、自動運転バスが注目されてます。また、沖縄では、もともと、鉄道網が発達しておらず、バスに頼る住民が多い状況があり、豊見城市にて実証実験を始めたとのことです。早ければ、2026年度に豊見城市の中心市街地の一部でレベル4の運行を目指してます。バスの運行路線の廃止は、住民の生活に直結する問題でもあり、日本国としては喫緊に取り組むべき課題です。
今回は、自動運転バスの状況について話します。
目次
- 自動運転バスについて
- 自動運転バスの状況について
- 自動運転バスの日本の状況について
- 中小企業の対応について
- アドバンス・キド株式会社からのご提案
- 自動運転バスについて
自動運転には、レベルが存在し、人間による運転はレベル0、条件が何もない中での完全自動運転がレベル5です。今、日本で多く行われている実証実験のほとんどがレベル2であり、まずは特定条件下(特定のルート等)で全運転操作が自動となるレベル4を目指してます。自動運転サービス導入に向けた課題のひとつは、必要な準備が多岐にわたることです。同時にインフラや法整備などの環境整備を進めることも、安全かつ円滑な自動運転バスには、非常に重要です。自動運転バスが走行する道路側の整備として、問えば、車から死角になるようなところでは、現在はカーブミラーが設置されてますが、自動運転車がカーブミラーから情報を得るのは難しいことから、死角になっている場所の情報をデジタル化して伝える必要があります。これが出来ると自動運転車の安全性はさらに高まります。また、専用レーンの確保や路上駐停車の管理や適正化さまざまな通信システムの整備なども重要です。自動運転は、車だけに関する技術ではなく、道路などの外部環境の整備と一体的に進めることが必要です。要するに街づくり含めて、自動運転バスを実現する必要があるということです。
- 自動運転バスの状況について
自動運転バスは、市民や業界から以下のメリットがあるといわれてます。
・人員不足の解消
・運転手のミスによる事故防止
・コスト削減
・過疎地域の移動手段の増加
・交通の円滑化
先日、閉幕しました関西万博の中でも自動運転バスが走ってました。そして、関西万博を契機に自動運転バスの導入が進んだのが大阪府です。万博では、センサーが設置された道路などの特定条件下で運転手がいらないレベル4に対応した車両で運行してました。自動運転区間外の対応で運転手は乗車してましたが、基本は自動運転です。乗客からは走行が滑らかで安心して乗れましたとの感想がありました。大阪市高速電気軌道(大坂メトロ)の河井社長は、万博を自動運転技術の実証の場と位置付け、大型車と中型車でレベル4に挑みました。この知見を活かして、2026年度から大阪府の南河内地域で一般客を乗せて、実証実験を計画してます。南河内地域は、運転手不足などが原因で路線バス15路線が統廃合された地域です。
京阪バス(京都)も万博に自動運転バスで参加し、万博会場の一部のアクセスで時速50キロメートルで走行しました。約1万5千人が乗車し、「安心して乗れたなどのポジティブな評価が多かった」様子で、手ごたえを感じたとのことです。市場調査MM総研によりますと、自動運転バス(レベル4以下対応)の走行台数は2022年12月の延べ17台から2024年12月には89台に急増してます。都道府県別では、大阪府の14台、茨城県の10台が続きます。
2020年11月に、全国で初めて公道で定期運行を始めたのが、茨城県境町です。町内には鉄道がなく、路線バスも市街に通じる幹線道路が中心で、橋本町長は、「自動車に頼らなくても住み続けられる仕組みが必要だった」と振り返ってます。現在は、8台を所有し、道の駅やショッピングセンター、病院などを結ぶっつのルート(各約8キロメート)を毎日、計33便、無料で運行しています。1日平均40~50人が利用し、累計の利用者数は、約4万3千人(2025年8月時点)にのぼるなど地域の足として根付いてます。利用者の中心は、高齢者で免許の返納が増えている状況があります。そのため、町では、高齢者による交通事故の件数が3割減ったとのことです。
3.沖縄での自動運転バスの状況について
豊見城市は、2024年に沖縄県内で初めて、路線バスの実証実験をしました。第一交通産業の子会社、琉球バス交通が協力し、生活路線である市内一周線(全長28キロメートル)の一部を利用して、実験をしてます。状況に応じて運転手がハンドルやブレーキを操作する「レベル2」で、23日間で市民ら約1800人が乗車しました。利用者アンケートでは、満足度が96パーセント、再利用の意向が92パーセントとニーズの高さが伺えます。さらに運転手がハンドルから手を放していた時間の割合を示す「自動運転率」は93パーセントに上がりました。レベル4の実現には、道路の状況をシステムが学習し、関連情報のデータを蓄積する必要があります。2025年11月からの実験では、前回に続いてレベル2ですが、期間を2か月半と前回の3倍以上の期間に拡大し、走行区間も約18キロメートルと前回の12キロメートルからのばす予定です。走行ルートのうち、市街地800メートルについては、早ければ2026年度にもレベル4を実現を目指します。徐々に無人自動運転の走行距離を伸ばしていく考えで、レベル4の運行には遠隔での運行管理監視がかかせず、NECシステムづくりを担当しています。
沖縄県内のバス運転手は、2022年度に1,640人と、5年間で1,000人以上減りました。残業規制の強化も相まって、路線バスは減便や廃止が続いてます。豊見城市は、自動運転の実現で「運転手不足でも減便せず、都市機能の充実を進めたい」と話してます。沖縄県では、豊見城市の他、南城市、石垣市も2024年にレベル2のバスの実証実験に取り組んでます。
4.中小企業の対応について
自動運転バスを実現するには、バスのセンサー技術も大事ですが、街のあらゆるところにセンサーを仕掛け、情報ネットワーク網をつくらないと実現できません。監視カメラも必要になります。常に自働運転バスが走る道の状況を監視する必要があります。また、気象情報や地震等の情報も必要です。迂回ルートのインプットも必要になります。自動運転バスは価格が高いので、安易に手が出せないという価格の障壁があります。みなさんでバスを改造して、自動運転用のバスを作ることも選択肢だと思ってます。皆さんで作ると、メンテナンスも皆さんが手掛ける必要があります。つまり、ハード面、ソフト面ともメンテナンスができる体制があると、今後の日本の各地域への広がりが期待できる様になります。
高度な技術社会ですが、ひとつひとつ切り分けると、手が届かない技術ではありません。
5.アドバンス・キド株式会社からのご提案
路線バスが動いていると、ホッとします。生活路線はもちろん、観光地にも欠かせない移動手段ではないでしょうか。自動運転バスが普及すると、街中の情報化は必然的に進みます。みなさんの会社の情報化は進んでいるでしょうか。最適なシステムは、途中で人の手を介さないシステムです。途中で人の手が加わると、間違いが起こる危険性が発生します。
来る街中の情報化を見据え、情報化への投資をご検討ください。投資額が心配な場合は、御社の電気代がどれだけ下るのか、電気代削減のシュミレーションを無料で実施します。試しにどこまで下がるのか、認識して頂き、切り替えたいと思った時期に切り替えるのが良いと思います。
自動運転バスの実現が待ち遠しいです。情報化社会が一挙に進みます。
以 上