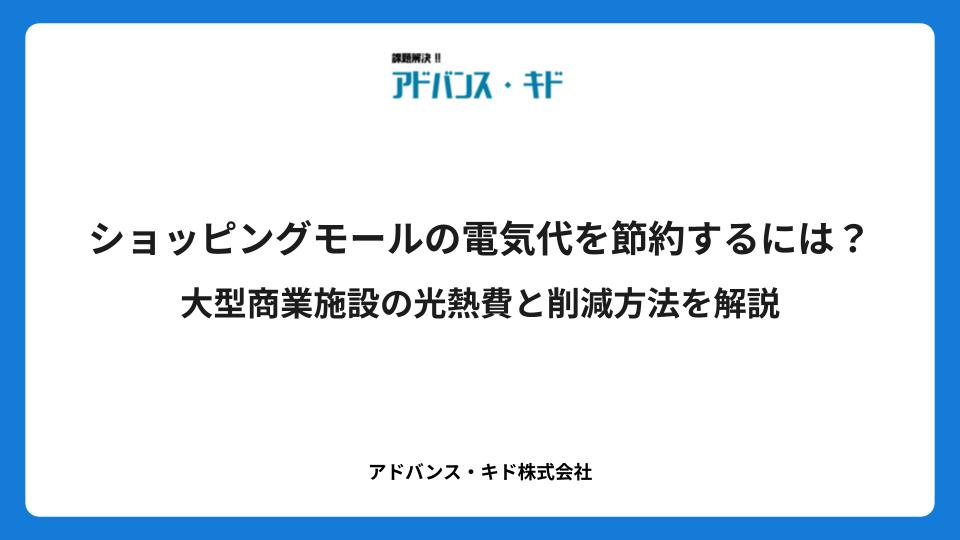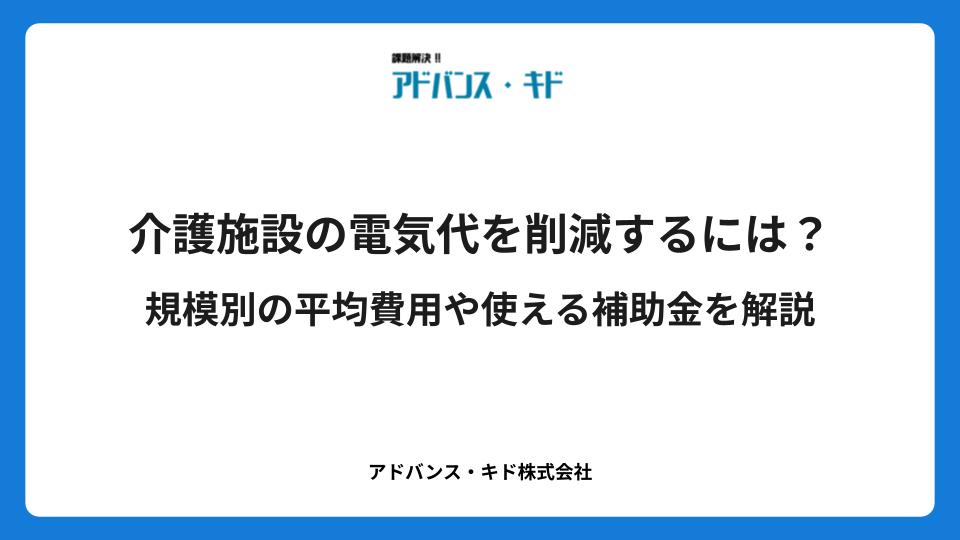記事公開日
オフィスの電気代の相場は?電気使用量の目安や内訳などを解説
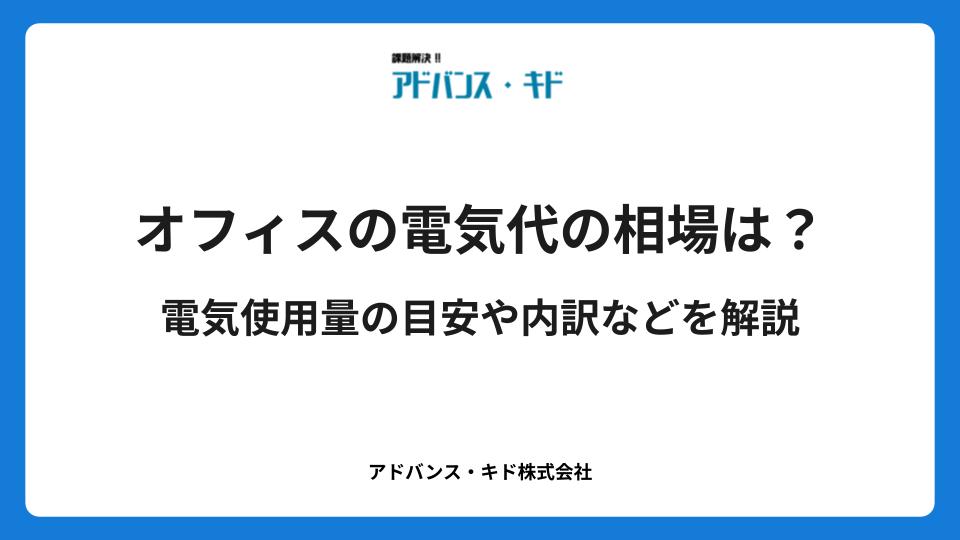
オフィスの電気代、高いとお悩みの方は多いのではないでしょうか。照明やエアコン、パソコンなど、電気を使う状況がかなり多いため、なかなか電気代の削減ができずにお困りの方も多いかもしれません。
本記事では、事業規模や業種、地域別の電気代相場から、オフィスの電気使用量の具体的な内訳まで解説します。照明や空調、OA機器など主要な設備の消費電力の目安を知ることで、自社の電気代が高い理由が明確になります。電気代を削減したい方は必見です。
オフィスの電気代相場と月額目安
オフィスの電気代は、事業規模、業種、地域、そして季節によって大きく変動します。ここでは、一般的なオフィスの電気代の相場と、月々の目安について解説します。
多くの企業が電気代の削減に関心を持っており、まずは自社の電気代が適正な範囲にあるのかを把握することが重要です。
事業規模別の電気代相場
オフィスの電気代は、その規模(延床面積や従業員数)に比例して変動します。主な事業規模別の電気代相場は以下の通りです。
小規模オフィス(SOHO・スタートアップなど、〜30坪程度、1〜10名): 月額1万円〜5万円程度が目安です。主に照明、PC、空調が主な電力消費源となります。
中規模オフィス(30坪〜100坪程度、10〜50名): 月額5万円〜20万円程度が一般的です。従業員数の増加に伴い、OA機器や空調の利用が増加します。
大規模オフィス(100坪以上、50名以上): 月額20万円以上、場合によっては数百万円に及ぶこともあります。ビル全体の空調システムやサーバー、多数のOA機器、セキュリティシステムなどが大きな電力消費源となります。
これらの金額はあくまで目安であり、使用する設備の種類や稼働時間、省エネ意識によって大きく変動します。
業種別の電気使用量の違い
オフィスの電気使用量は、事業内容や業種によって大きく異なります。特に電力消費が大きい業種と、比較的少ない業種があります。
電力消費が多い業種
製造業: 生産ラインの機械設備や大型モーター、溶接機などが大量の電力を消費します。
飲食業: 厨房の冷蔵庫、冷凍庫、オーブン、IH調理器、換気扇などが長時間稼働するため、電気使用量が高くなりがちです。
美容室・理容室: ドライヤー、シャンプー台、照明などが主な電力消費源です。
医療機関: 医療機器、検査機器、24時間稼働のサーバー、空調などが多くの電力を必要とします。
データセンター・IT企業: サーバーやネットワーク機器の冷却、安定稼働のための空調が非常に重要であり、莫大な電力を消費します。
比較的電力消費が少ない業種:
一般的な事務オフィス(IT、コンサルティング、士業など): 主にPC、照明、空調が中心で、特殊な機器を使用しないため、他の業種と比較して電気使用量は抑えられる傾向にあります。
自社の業種特性を理解し、どの設備が電力消費の大部分を占めているのかを把握することが、効果的な電気代削減の第一歩となります。
地域別の電気料金単価の差
日本の電気料金は、地域によって契約する電力会社や料金単価が異なります。主に大手電力会社10社(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)の供給エリアに分かれています。
各電力会社はそれぞれ異なる料金体系を設定しており、基本料金や電力量料金(従量料金)の単価に差があります。また、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金は全国一律ではなく、毎月変動する燃料価格や国の政策によっても電気代は影響を受けます。
さらに、契約する料金プランによっては、昼間と夜間、平日と休日で単価が異なる「時間帯別料金」や、季節によって単価が変わる「季節別料金」なども存在します。自社の事業所の所在地と、現在の契約プランを確認することが、適正な電気料金を把握する上で重要です。
オフィスの電気使用量の内訳
オフィスの電気代を削減するためには、まず何にどれくらいの電力が使われているかを把握することが重要です。一般的に、オフィスの電気使用量は空調、照明、OA機器の3つが大きな割合を占めます。
主要な電気使用設備と消費電力
オフィスで電気を消費する主な設備は、快適な執務環境を保つための空調設備、作業効率を高める照明設備、そして業務に不可欠なOA機器です。これらの設備がオフィスの総消費電力の大部分を占めており、それぞれに消費電力の特性があります。
例えば、空調設備は季節や設定温度によって消費電力が大きく変動します。照明設備は点灯時間や設置されている電球の種類によって消費電力が異なります。また、パソコンや複合機などのOA機器は、その台数や使用状況によって電力消費量が積算されます。
これらの主要設備以外にも、給湯器、冷蔵庫、ウォーターサーバーなども電気を消費します。それぞれの設備の消費電力を把握することで、効果的な省エネ対策の検討が可能になります。
照明設備の電気使用量
オフィスにおける照明設備は、一般的に総電気使用量の約20%~30%を占めると言われています。特に、日中の執務時間帯は常に点灯しているため、その積算消費電力は大きなものとなります。
従来の蛍光灯は消費電力が比較的高く、寿命もLED照明に比べて短い傾向にあります。一方、LED照明は消費電力が少なく、長寿命であるため、近年では多くのオフィスで導入が進んでいます。照明の明るさや色温度、設置台数、点灯時間なども電気使用量に大きく影響します。
空調設備の電気使用量
オフィスの電気使用量の中で最も大きな割合を占めるのが空調設備です。一般的に、オフィス全体の電気使用量の約50%近くが空調によるものとされています。特に夏場の冷房と冬場の暖房は、外気温と設定温度の差が大きくなるため、消費電力が急増する傾向にあります。
エアコンの消費電力は、機種の能力、運転モード、設定温度、外気温、室内の広さ、断熱性能など多くの要因によって変動します。
古いタイプのエアコンは最新の省エネ型エアコンに比べて消費電力が大きいことが多く、導入から年数が経過している場合は、より多くの電気を消費している可能性があります。
OA機器の電気使用量
オフィスで日常的に使用されるOA機器(オフィスオートメーション機器)も、積算するとかなりの電気を消費します。主なOA機器には、パソコン、ディスプレイ、プリンター、複合機、サーバー、ルーターなどがあります。
個々の機器の消費電力はそれほど大きくなくても、オフィス内に多数設置されているため、その合計は無視できません。特に、サーバーのように24時間稼働している機器や、複合機のように常に待機電力を消費している機器は、継続的な電力消費源となります。
また、パソコンやディスプレイのスタンバイモードやスリープモードでも、わずかながら電力を消費しています。使用しない時間は電源を切る、省電力設定を適切に行うといった対策が、OA機器による電気使用量の削減につながります。
オフィスの電気代を削減する方法
LED照明への切り替え効果
オフィスの電気代削減において、照明は大きな割合を占める電気使用源の一つです。特に古い蛍光灯や白熱灯を使用している場合、LED照明への切り替えは劇的なコスト削減効果をもたらします。
LED照明は、従来の蛍光灯と比較して消費電力を約50%~70%、白熱灯と比較すると約80%~90%削減できるとされています。これにより、毎月の電気料金を大幅に抑えることが可能です。また、LED照明は寿命が非常に長く、約40,000時間から60,000時間と、蛍光灯の数倍から数十倍に及びます。この長寿命化により、ランプ交換の手間や費用といったメンテナンスコストも削減でき、長期的な視点で見ると大きな経済的メリットがあります。
初期投資は必要ですが、削減される電気代とメンテナンスコストを考慮すると、比較的短期間で投資回収が見込めます。さらに、LED照明はCO2排出量の削減にも貢献し、企業の環境配慮への取り組みとしても有効です。
省エネ空調設備の導入
オフィスにおける電気代の約半分を占めるとも言われる空調設備は、電気代削減の鍵となる要素です。特に古いタイプの空調設備を使用している場合、最新の省エネ型空調設備への入れ替えを検討することで、大幅な電気代削減が期待できます。
最新の空調設備には、高効率なインバーター制御や高性能な熱交換器が搭載されており、必要な能力に応じて運転を最適化することで無駄な電力消費を抑えます。選定の際には、APF(通年エネルギー消費効率)などの省エネ性能指標が高い機種を選ぶことが重要です。APFは、年間を通してどの程度の効率で運転できるかを示す指標であり、数値が高いほど省エネ性能に優れています。
また、空調設備の導入だけでなく、定期的なフィルター清掃やメンテナンスも省エネ効果を持続させる上で不可欠です。フィルターが目詰まりすると、空気の循環が悪くなり、余計な電力を消費してしまいます。さらに、夏場の設定温度を28℃、冬場を20℃に保つなど、運用面での適切な温度管理も併せて行うことで、さらなる節電効果が得られます。
電力会社の見直しと契約プラン変更
2016年の電力小売自由化以降、企業は様々な電力会社や料金プランの中から、自社の電力使用状況に最適なものを選べるようになりました。現在契約している電力会社やプランを定期的に見直すことで、電気代を削減できる可能性があります。
既存の大手電力会社でも、時間帯別料金プランやピークカット型プランなど、多様なプランを提供しています。自社の電力使用パターン(例えば、日中のオフィスアワーに集中するのか、夜間や休日も稼働するのかなど)を分析し、最も有利な料金体系のプランを選択することが重要です。
また、契約アンペア数(契約電力)が自社の実態に合っているかどうかの見直しも重要です。過剰な契約アンペア数は基本料金を高くしてしまうため、過去の最大デマンド値を参考に適切な契約電力に設定し直すことで、基本料金を削減できる場合があります。複数の電力会社の料金プランを比較検討し、自社の事業規模や業種に合った最適なプランを見つけることが、電気代削減への第一歩となります。
電力を切り替えるなら『アドバンス・キド』の新電力
電力自由化の恩恵を最大限に活用するためには、新電力会社への切り替えも有力な選択肢となります。新電力会社は、大手電力会社とは異なる独自の料金プランやサービスを提供しており、企業の電気代削減に貢献する可能性があります。
アドバンス・キドは、新電力への切り替えで年間最大30%ものコスト削減と安心の電力供給を両立させます。そのため、電気代の高騰にお悩みの法人の方にぴったりなサービスとなっております。
①最適なプランをご提案する専門性
お客様の過去1年間の電気使用状況を詳細に分析し、最適な新電力会社・電力プランを厳選します。低圧・高圧問わず対応可能で、シミュレーションにより削減額を明確にした上でご提案。多様な業種で月間23%〜36%の削減実績がある、オーダーメイドの提案力が強みです。
②市場連動型の不安を解消し、安定性を重視
電気料金の変動リスクを抑えるため、安定的な料金設定のプランを扱う新電力会社を厳選。ご要望に応じて固定料金型プランもご紹介可能です。市場データに基づいた詳細なシミュレーションで、変動リスクを分かりやすくご説明し、お客様の納得感を重視した安心できるプラン選択をサポートします。
③経営基盤が安定した「信頼できる新電力会社」のみを厳選
お客様のビジネス基盤を守るため、経営基盤が安定し、長期的な継続供給が可能な信頼性の高い新電力会社のみを厳選しています。大手商社や大手銀行が株主についているなど、財務状況が安定した企業との提携により、お客様は「倒産リスク」の心配なく安心してご利用いただけます。
電気代削減、そして削減したコストの利活用にご興味があれば、まずはお気軽に無料シミュレーションをご依頼ください。貴社の電気代がどれだけ削減できるかをご確認いただけます。
アドバンス・キドの新電力はこちら
https://www.adkd.co.jp/shindenryoku/
新電力に関するご相談・お問い合わせはこちら
https://www.adkd.co.jp/contact/
まとめ:オフィスの電気代を見直そう
オフィスの電気代は事業規模や業種、地域によって大きく異なりますが、内訳を正確に把握し、適切な対策を講じることで大幅な削減が可能です。
照明のLED化や省エネ空調設備の導入は初期投資がかかるものの、長期的な視点で見れば確実なコストダウンに繋がります。さらに、電力会社の契約プランを見直したり、新電力への切り替えを検討することも非常に効果的です。自社に最適なプランを見つけることで、継続的な電気代削減と経営効率の向上が期待できるでしょう。