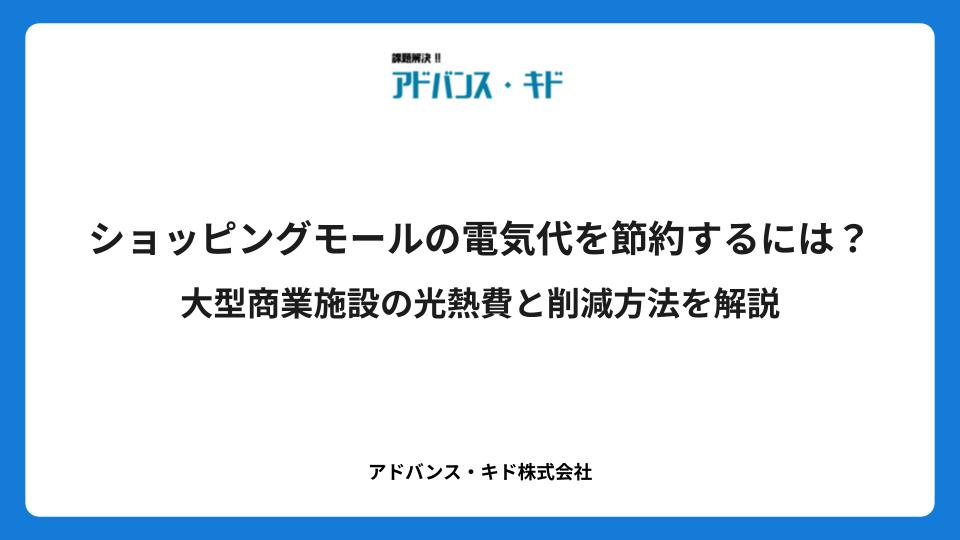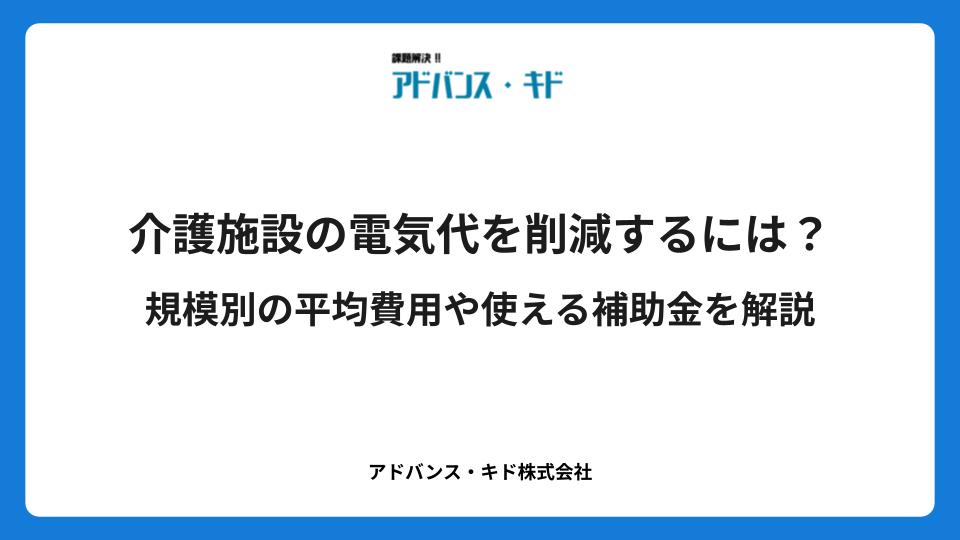記事公開日
マンション共有部のコストを削減するには?今すぐ見直すべき理由と対策方法をご紹介
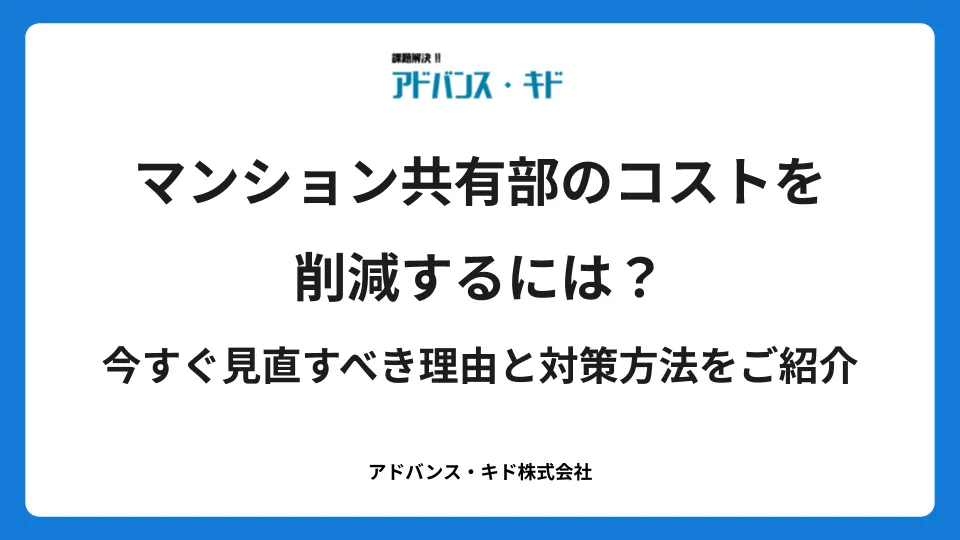
皆様が所有・管理するマンションの「共用部の電気代」、ここにはコスト削減の伸びしろがある可能性があります。
「照明のLED化は済ませたし、これ以上の対策は…」 「日々の業務に追われ、固定費の見直しまで手が回らない」
多くの方がそう考えるていますが、そんな中でも電気代の高騰はとどまることを知らず、知らず知らずのうちに会社の利益を圧迫し続けています。
しかし、この問題を見て見ぬふりをすれば、数年後には競合との収益性に大きな差となって表れるかもしれません。
本記事では、今すぐ着手できる具体的なコスト削減策はもちろん、多くの経営者がまだ気づいていない、利益率をV字回復させるための「抜本的な対策」まで、プロの視点から徹底的に解説します。コスト削減の次の一手をお探しの経営者様は、ぜひ最後までご一読ください。
なぜ今、マンション共用部の電気代対策が「経営課題」なのか?
日々の経営判断の中で、マンションの共用部電気代は後回しにされがちな項目かもしれません。しかし、近年の社会情勢の変化により、その認識は「経営リスク」へと変わりつつあります。
止まらない電気料金の値上げ、その背景と今後の見通し
ご存知の通り、日本の電気料金は上昇の一途をたどっています。その背景には、化石燃料の価格高騰、円安の進行、再生可能エネルギー賦課金の負担増など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
重要なのは、この傾向が短期的なものではなく、今後も継続する可能性が高いという点です。経営者として、この外部環境の変化に対応しない手はありません。コスト構造を根本から見直すことが、企業の持続的な成長に不可欠です。
「共用部の電気代」がマンション経営の利益を圧迫するメカニズム
マンション経営において、共用部の電気代は「管理費」から支出される代表的な固定費です。つまり、電気代が上昇すればするほど、マンションの運営利益は直接的に減少します。
このコストを放置することは、気づかぬうちに企業の体力を削いでいくことに他なりません。
コスト削減の最後のフロンティア、それが共用部電力
多くの企業がオフィスや店舗の節電対策には熱心ですが、マンションの共用部については、一度設置した設備をそのまま使い続けているケースが少なくありません。
ここを改善することができれば、他社との差別化、そして収益性の向上に直結します。
まずは現状把握から!自社物件の共用部電気代は高いのか?
対策を講じる前に、まずは自社が管理する物件の現状を正確に把握することが重要です。
マンション共用部の電気代、主な内訳とは?
共用部の電気は、マンションの快適性と安全性を維持するために不可欠な様々な設備で利用されています。
- 共用灯・廊下灯
- エレベーター
- 給水ポンプ、排水ポンプ
- オートロック、自動ドア
- 駐車場(機械式駐車場、照明など)
- インターネット設備
これらの設備が24時間365日稼働することで、電気代は積み重なっていきます。
【規模別】共用部電気代の料金相場と計算方法
物件の規模や設備によって大きく異なりますが、一般的な料金相場は以下の通りです。
- 単身者向けマンション(20~30戸): 20,000円~40,000円/月
- ファミリー向けマンション(50戸前後): 50,000円~80,000円/月
- 大規模マンション(100戸以上): 100,000円~/月
※上記はあくまで目安です。エレベーターの基数や機械式駐車場の有無で大きく変動する可能性もあります。
自社の請求額がこの相場から大きく乖離している場合は、早急な対策が必要です。
電気代の検針票でチェックすべき3つの重要項目
お手元に電気の検針票(電気ご使用量のお知らせ)をご用意ください。検針票の中で、最低限チェックすべき点は以下の3点です。
- 契約種別: 「低圧電力」「高圧電力」など、どの契約プランになっているか。
- 契約電力: 基本料金を決める数値(kW)。この数値が適正かどうかがポイントです。
- 使用電力量: 実際に使用した電力量(kWh)。季節によってどう変動するかを確認します。
これらの数値を把握することが、的確なコスト削減策の第一歩となります。
【Step1:応急処置】多くの管理会社が実践する基本的なコスト削減策
まずは、比較的着手しやすく、多くのマンションで導入されている基本的な対策をご紹介します。
共用灯・廊下灯のLED化
最も代表的な手法です。従来の蛍光灯からLEDに交換するだけで、照明部分の消費電力を約50%~70%削減できると言われています。初期費用はかかりますが、長期的に見れば確実なコスト削減に繋がります。
電子ブレーカー導入による基本料金の削減
マンションの共用部は、常に最大の電力が使われるわけではありません。電子ブレーカーは、実際の使用状況に合わせて電気の基本料金を最適化する装置です。契約電力を下げることができるため、毎月の固定費である基本料金の削減が期待できます。
人感センサーやタイマー設置による無駄の排除
使用頻度の低い廊下や階段、駐車場などに人感センサー付きの照明を導入することで、不要な点灯時間を削減できます。誰もいない時間は消灯するため、効率的な電力使用が可能です。
【Step2:抜本的改革】経営者が取り組むべき「電力単価」そのものの見直し
応急処置だけでは、高騰し続ける電気代にはいずれ追いつかれてしまいます。経営者が取り組むべきなのは、より抜本的な改革です。
なぜ基本的な対策だけでは限界があるのか?
電気料金は、大きく分けて「①基本料金」と「②電力量料金」で構成されています。
- ①基本料金: 電気の使用量に関わらず毎月かかる固定費
- ②電力量料金: 電気の使用量に応じてかかる変動費(単価 × 使用量)
Step1でご紹介した対策は、主に「②電力量料金」の中の「使用量」を減らすためのものです。しかし、「単価」そのものが高騰し続ければ、努力の効果は半減してしまいます。
コスト削減の鍵は「基本料金」と「電力量料金」の抜本的見直し
真のコスト削減を達成するには、使用量を減らす努力と同時に、料金の根幹である「基本料金」と「電力量料金の単価」そのものを引き下げるアプローチが不可欠です。
解決策は「電力会社の切り替え」。新電力という選択肢
その最も有効な解決策が、電力会社の切り替えです。2016年の電力自由化以降、私たちは地域の大手電力会社だけでなく、「新電力」と呼ばれる新しい電力会社を自由に選べるようになりました。そして、この「新電力」こそが、マンション共用部の電気代を劇的に削減する鍵となるのです。
なぜ「新電力」がマンション共用部の電気代削減に有効なのか?
「電力会社を変えるだけで、なぜ安くなるのか?」 「電気の品質が落ちたり、停電しやすくなったりしないか?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?その仕組みとメリットを解説します。
電力自由化の仕組みを経営に活かす方法
電力自由化とは、例えるなら携帯電話会社を自由に乗り換えられるのと同じです。どの会社の電気を使っても、送られてくる電気はこれまでと同じ送電網を経由します。そのため、電力の品質や安定供給は、切り替え前と全く変わりません。停電のリスクが高まることも一切ありません。
初期費用・工事不要で電気代が安くなる理由
新電力は、大手電力会社とは異なる独自の電源調達方法や、経営努力によって、より安価な料金プランを提供しています。切り替えに際して、原則として初期費用や大掛かりな工事は不要です。つまり、経営リスクを負うことなく、電気代という固定費の削減メリットだけを享受できるのです。
アドバンス・キドの新電力サービスが選ばれる理由
数ある新電力の中でも、私たちアドバンス・キドは、特に中小企業の皆様のマンション経営をサポートすることに強みを持っています。
中小企業のマンション経営に寄りそう料金プランのご提案
私たちは、画一的なプランを提供するだけではありません。お客様の物件の規模、設備、電力使用状況を詳細に分析し、最もコスト削減効果の高いオーダーメイドの料金プランをご提案します。
安定供給と安心のサポート体制
電力の安定供給はもちろんのこと、ご契約からアフターサポートまで、ワンストップで丁寧に対応いたします。多忙な経営者様のお手を煩わせることはありません。
まとめ:共用部の電気代見直しは、経営改善に向けた未来への投資
本記事の要点を振り返ります。
- 電気代高騰は今後も続く可能性が高く、放置は経営リスクとなる。
- LED化などの対策に加え、「電力単価」そのものを見直す抜本改革が必要。
- その解決策が、品質を変えずにコストだけを削減できる「新電力」への切り替え。
マンション共用部の電気代削減は、単なる経費節減ではありません。そこで生み出されたキャッシュフローは、新たな設備投資や修繕積立金に充当でき、物件そのものの資産価値を高める「未来への投資」に繋がります。
競合がまだ気づいていない今だからこそ、行動を起こすチャンスです。
まずは貴社のマンションで、一体どれくらいのコストが削減できるのか、確認してみませんか?